宅建試験の受験生の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法の中でも非常に出題頻度が高く、実務でも重要な「広告規制」について詳しく解説します。
広告は不動産取引の入り口となる部分ですので、消費者保護のために厳しい規制が設けられており、宅建試験でも必ずといっていいほど問われる分野です。
本記事では「誇大広告の禁止」「広告の開始時期の制限」「取引態様の明示」について、例題を交えながらわかりやすく整理していきます。
誇大広告等の禁止について理解しよう
宅建業者が広告を出すときには、事実と異なる表示、または著しく事実と異なる表示をしてはいけないと宅建業法で定められています。
特に次のような表示は禁止されています。
- 実際に取引する意思のない物件を表示する「おとり広告」
- 実際より著しく優良・有利に見せかける誤解を招く広告
- 物件が存在しない、または取引できないものを表示する虚偽広告
もしこれに違反した場合、監督処分や罰則(6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金、またはその併科)を受けることになります。
重要なのは、実際に被害が出たかどうかに関係なく、広告を出しただけで違反になる点です。
誇大広告の対象となる項目
誇大広告等の禁止の対象となるのは、以下の具体的な内容です。
- 物件の所在
- 規模(敷地面積・建物の延床面積など)
- 形質(土地の種類・建物の構造)
- 利用制限(建ぺい率・容積率・用途地域など)
- 周囲の環境
- 交通の利便性
- 価格・賃料・支払い方法
- 金銭の貸借のあっせん
これらの情報を広告する際には、事実と異なる表示や誤解させるような表現をしてはいけません。
例題で確認しよう
例題1
A宅建業者は、駅から徒歩20分の物件について「駅徒歩10分」とチラシに記載して広告を出しました。この場合の法的な取扱いとして正しいものはどれか。
A. 被害者がいなければ問題ない
B. 誇大広告となり宅建業法違反
C. 物件の価格に関する事項ではないので問題ない
D. 特に問題なし
正解と解説
→B
事実と異なる表示は誇大広告に該当し、宅建業法違反です。被害の有無は関係ありません。
広告の開始時期の制限
未完成物件の広告には特に厳しい制限があります。
未完成の分譲住宅やマンションなどの物件は、工事に必要な「開発許可」や「建築確認」を受けた後でなければ広告を行ってはならないとされています。
なぜなら、許可を受ける前に広告を行うと、誇大広告の恐れがあるからです。
特に以下の点を覚えておきましょう。
- 申請中の段階では広告不可
- 許可後なら広告可能
- 許可を受けていないプランを広告する場合、注意書き必須
例題で確認しよう
例題2
宅建業者B社は、建築確認申請中の未完成物件について、「建築確認後に契約可能」との注記を付けて広告を出しました。この場合、法的に正しいのはどれか。
A. 契約前なら広告可能
B. 建築確認申請中なら広告してもよい
C. 注記しても広告不可
D. 特例として広告可能
正解と解説
→C
建築確認申請中では、注記しても広告はできません。許可後でなければ違反となります。
変更確認の取り扱いについて
当初の確認後、建築計画を変更する場合は「変更確認」を受ける必要があります。
この際、以下のように広告の取扱いが変わります。
- 変更確認申請中でも、当初確認の内容なら広告可能
- 変更確認を予定している旨と当初内容を併記すれば、変更予定の内容も表示可能
- 建築確認を受けていないプランは、確認が必要である旨を表示すれば差し支えない
この扱いは例題としてもよく出題されます。
例題3
建築確認を受けたプランと、未確認のセレクトプランを併記する場合、必要な対応として正しいものはどれか。
A. 確認済のプランだけ表示すればよい
B. 確認を受けていない旨を明記すれば併記可能
C. どちらも自由に記載できる
D. セレクトプランは広告できない
正解と解説
→B
建築確認を受けていない旨を表示すれば、併記可能です。これが宅建業法上の正しい取扱いです。
取引態様の明示義務
宅建業法では、物件の広告や注文の際に、必ず「取引態様」を明示することが義務付けられています。
取引態様とは、自ら売主・代理・媒介(仲介)といった、宅建業者としての取引形態をいいます。
- 広告時に必ず明示(表示義務)
- 注文を受けたときにも遅滞なく明示(口頭でも可)
注意点
広告で明示したからといって、注文を受けたときに再度明示しなくてよいわけではありません。注文時にも必ず改めて明示が必要です。
例題4
C宅建業者が媒介として広告を行い、顧客から注文を受けたとき、次のうち正しいのはどれか。
A. 注文時の明示は不要
B. 広告に記載したから明示は省略できる
C. 口頭でもよいので注文時に取引態様を明示する
D. 明示は売買契約締結時でよい
正解と解説
→C
注文時には口頭でもよいので必ず取引態様を明示しなければなりません。広告時の明示とは別に必要です。
宅建試験攻略アドバイス
この広告規制分野は、以下の点を重点的に押さえてください。
- 誇大広告は被害の有無を問わず違反
- おとり広告のパターン(存在しない・取引できない・意思がない)
- 未完成物件は建築確認後でないと広告不可
- 取引態様は広告時と注文時で必ず明示
- 変更確認時の広告の条件
これらを例題付きで何度も復習し、実際の出題パターンに慣れておきましょう。
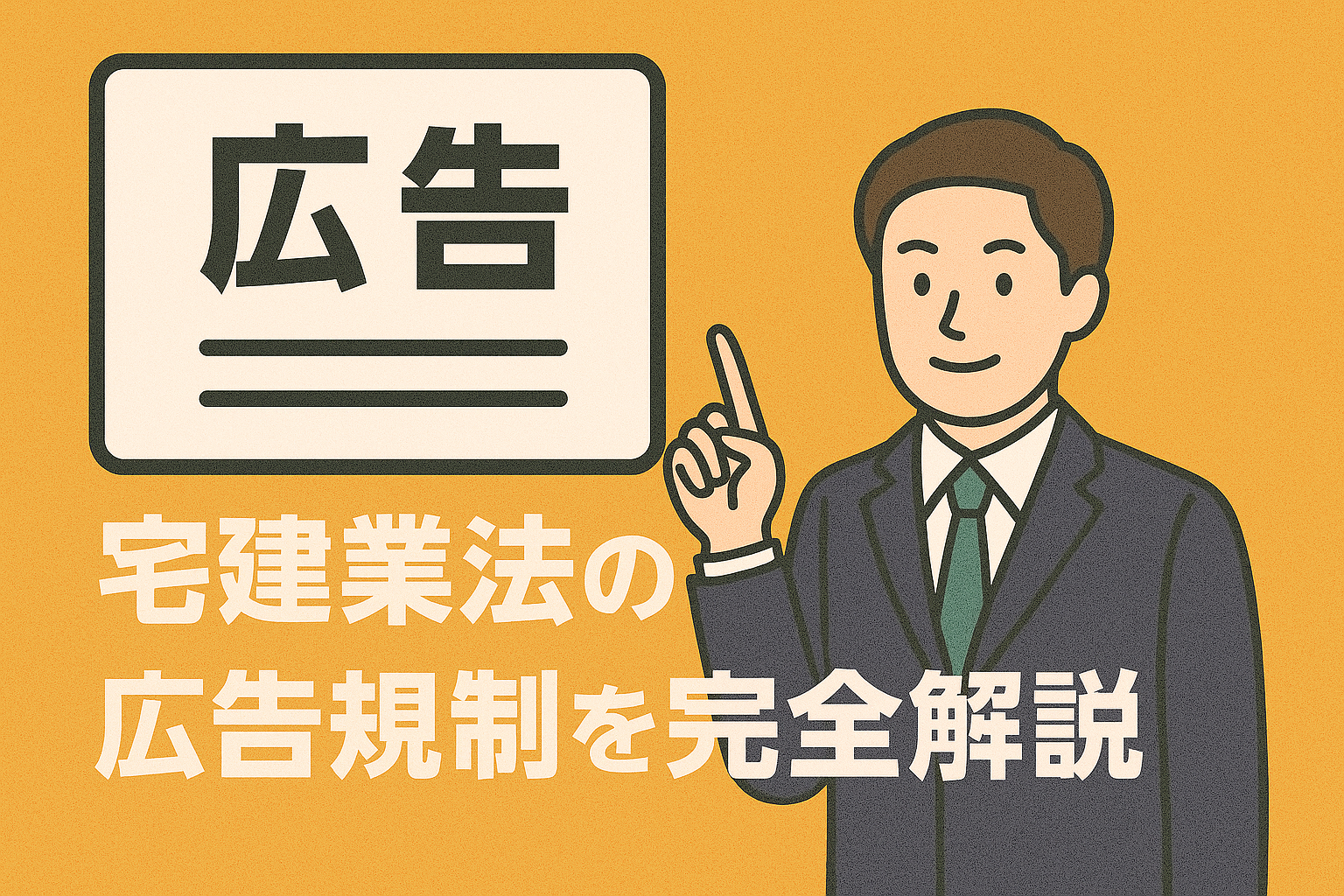
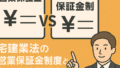
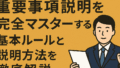
コメント