宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
2025年も、日本の各地で記録的な大雨のニュースが頻繁に報じられています。こうした気候変動の現実は、私たちが暮らす土地の安全性について、これまで以上に真剣に考えることを求めています。そして、この「土地の安全性」というテーマは、宅建試験において、そして皆さんが将来宅建士として働く上で、極めて重要な意味を持ちます。今回は、この時期だからこそ改めて深く学びたい「ハザードマップ」と、それに伴う宅建士の法的義務について解説します。
「ハザードマップ」とは何か まずは基本の確認
まず基本の確認です。ハザードマップとは、自然災害による被害の予測範囲やその程度、そして避難場所などの情報を視覚的に表示した地図のことを指します。主に市町村などの地方自治体が作成・公表しており、洪水、内水氾濫、高潮、土砂災害、地震など、災害の種類ごとに様々なマップが存在します。これにより、住民は自らの居住地の災害リスクを事前に把握することができます。
宅建業法における最重要項目「水害ハザードマップ」の説明義務
ここからが本題です。宅建受験者として絶対に覚えなければならないのが、このハザードマップが「重要事項説明」の必須項目であるという点です。特に、2020年8月の宅地建物取引業法施行規則の改正により、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地について説明することが、売買・交換・貸借のすべての取引において義務化されました。これは、近年の水害の激甚化・頻発化を背景とした、非常に重要な法改正です。
具体的に何をどこまで説明する必要があるのか
では、重要事項説明では、具体的に何をすればよいのでしょうか。法律が求めているのは、「ハザードマップを提示し、そのマップ上における当該物件の位置を示すこと」です。説明の対象となるのは、「洪水」「内水(下水道等の排水施設の能力を超えた大雨による浸水)」「高潮」の3種類の水害ハザードマップです。宅建士は、これらのマップを入手し、取引相手に対して「あなたが契約しようとしている物件は、このハザードマップ上ではこの場所にあります」と指し示す義務があるのです。
土砂災害警戒区域との違いと注意点
ここで、学習が進んでいる方は「土砂災害警戒区域」の説明義務との違いを明確に区別する必要があります。「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律」に基づく説明義務は、以前から存在していました。2020年の法改正は、これに加えて、水害ハザードマップの説明を義務化したものです。つまり、対象物件が土砂災害警戒区域内にある場合はその旨を、そして水害ハザードマップ上での位置も、それぞれ説明する必要があるのです。混同しないよう、しっかりと整理しておきましょう。
単なる義務ではない 命と財産を守るための重い責任
最後に、宅建士としての心構えについてです。ハザードマップの説明は、単に法律で決まっているから行う事務的な作業ではありません。これは、顧客の「命」と「財産」を守るための、極めて重い責任を伴う行為です。説明を怠ったり、不十分だったりした結果、顧客が水害に遭ってしまった場合、宅建士は法的な責任を問われるだけでなく、取り返しのつかない事態を招くことになります。なぜこの規定が作られたのか、その背景にある社会的な要請を深く理解すること。それが、信頼される不動産のプロフェッショナルになるための第一歩です。試験で学ぶ一つひとつの知識が、現実の人の暮らしに直結していることを常に意識し、学習に励んでください。

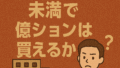
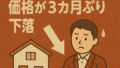
コメント