はじめに
賃貸不動産経営管理士試験では、民法の「契約に関する基本原理」が非常に重要なテーマです。
特に、管理受託契約がどのような法律関係で構成されているか(委任・請負・賃貸借の違い)を理解しておくことが得点のカギとなります。
本記事では、権利能力や意思能力から始まり、制限行為能力、委任・請負・賃貸借の違い、さらに借地借家法・契約締結上の過失までを体系的に整理します。
試験に出やすいポイントを「例題付き」でわかりやすく解説します。
権利能力と意思能力の基本
■権利能力とは?
「権利能力」とは、権利を取得したり義務を負担できる資格のことです。
自然人(人間)と法人(会社など)に認められており、これがなければ契約の当事者になることができません。
■意思能力とは?
「意思能力」とは、自分の行為の結果を理解できる精神的な能力をいいます。
目安としては7歳~10歳程度の理解力です。
意思能力を欠く者(幼児や泥酔者など)が行った契約は無効です(民法3条の2)。
制限行為能力者と保護者の関係
意思能力があっても、判断力が不十分な人を保護するために、民法は「制限行為能力者制度」を設けています。
該当者は次の4種類です。
| 種類 | 典型例 | 保護者 | 同意権 | 取消権 | 代理権 |
|---|---|---|---|---|---|
| 未成年者 | 18歳未満 | 親権者・未成年後見人 | あり | あり | 法定代理人としてあり |
| 成年被後見人 | 重度の精神障害者 | 成年後見人 | なし | あり | 法定代理人としてあり |
| 被保佐人 | 判断力が著しく不十分 | 保佐人 | 特定の行為のみあり | あり | 審判で特定付与 |
| 被補助人 | 判断力が不十分 | 補助人 | 特定の行為のみあり | あり | 審判で特定付与 |
💡未成年者の単独でできる行為
- 負担のない贈与を受ける(権利を得るだけの行為)
- 親から許された小遣いの範囲で物を買う
- 営業の許可を受けた場合の営業行為
💡成年被後見人
判断能力が欠けているため、法律行為をしても後から取り消せます(9条)。
ただし、日用品の購入など日常生活行為は有効です。
また、成年後見人が代理して居住用不動産を処分する場合は家庭裁判所の許可が必要です(859条の3)。
管理受託契約の性質 ― 委任・準委任・請負の関係
管理受託契約は、賃貸人から委託を受けて物件管理を行う契約であり、
民法上は次のように分類されます。
| 行為内容 | 契約の種類 |
|---|---|
| 契約行為(入居契約など)を代理して行う | 委任契約 |
| 清掃・点検などの事務処理を行う | 準委任契約 |
| 修繕など「仕事の完成」が目的 | 請負契約 |
■委任契約と請負契約の違い
| 比較項目 | 委任契約 | 請負契約 |
|---|---|---|
| 契約目的 | 事務処理(法律行為) | 仕事の完成 |
| 成立要件 | 合意で成立(諾成契約) | 合意で成立(諾成契約) |
| 報酬 | 無償が原則、有償も可 | 有償が原則 |
| 性質 | 信頼関係重視 | 結果重視 |
| 終了事由 | 当事者の死亡など | 仕事完成・解除など |
委任契約の基本と受任者の義務
■委任契約の成立
「委任契約」とは、法律行為を委託し、受任者が承諾することで成立する契約です(643条)。
法律行為でない事務処理の場合は「準委任契約」となります(656条)。
■受任者の主な義務
- 善良な管理者の注意義務(644条)
- 受取物の引渡義務(646条)
- 報告義務(645条)
違反すると債務不履行責任を負います。
■委任契約の解除と終了
委任契約は信頼関係が基盤のため、いつでも解除可能です(651条)。
ただし、相手方に不利益が生じる時期に解除した場合は、損害賠償が必要です。
また、当事者の死亡や破産でも終了します(653条)。
管理受託契約でも、建物所有者が死亡しても契約は終了しません(法人契約のため)。
請負契約 ― 「結果責任」を問われる契約
■請負契約の定義
請負とは、「ある仕事を完成することを約し、その報酬を受け取る契約」です(632条)。
代表例は、建物修繕・リフォーム・原状回復工事などです。
■報酬支払の原則
仕事完成後、引渡しと同時に報酬を支払います(633条)。
途中で解除された場合でも、既に完成した部分については利益の割合に応じた報酬を請求できます(634条)。
■請負人の担保責任
仕事が契約内容に適合しない場合、次の請求が可能です。
| 種類 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 追完請求 | 562条 | 修補や代替引渡しを請求できる |
| 報酬減額請求 | 563条 | 不適合の程度に応じ減額可能 |
| 損害賠償請求 | 564条 | 契約違反による損害を請求できる |
| 契約解除 | 541条・564条 | 相当期間経過後も履行しない場合 |
■期間制限
不適合を知ったときから1年以内に通知しないと権利を失います(637条)。
賃貸借契約 ― 試験で最も出る基本契約
賃貸借とは、物を使用・収益させることを約し、賃料を支払う契約です(601条)。
契約は書面でなくても成立する「不要式・諾成契約」です。
💡借地借家法との関係
借地借家法は、賃借人保護を目的とした特別法であり、民法よりも優先されます。
建物の賃貸借(借家契約)や土地の借地契約にはこの法律が適用されます。
ただし、次の契約は適用外です。
- 建物所有を目的としない土地の賃貸借
- 無償の使用貸借
契約締結上の過失 ― 契約前でも責任を問われる!
契約交渉が進展して相手に信頼を与えた後、一方的に交渉を破棄した場合は「契約締結上の過失責任(culpa in contrahendo)」が生じることがあります。
この責任は不法行為による損害賠償責任とされています(最判平23・4・22)。
■判例例示
- 美容院開業予定者への一方的な契約拒否 → 賃貸人に責任(神戸地判平10・6・22)
- 外国人であることを理由に拒否 → 賃貸人に責任(大阪地判平5・6・18)
- 賃借希望者が合意後に破棄 → 賃借人に責任(東京高判平30・10・31)
共有物の賃貸と決定権
共有建物を貸す場合、その契約は「管理行為」にあたり、持分の過半数で決定します(252条)。
3年以内の賃貸借は「管理」、5年以上の契約は「変更」となり、全員の同意が必要です。
💡保存・管理・変更のまとめ
| 行為区分 | 具体例 | 決定要件 |
|---|---|---|
| 保存行為 | 修繕・妨害排除 | 単独で可能 |
| 管理行為 | 賃貸借契約の解除・期間決定 | 持分の過半数 |
| 変更行為 | 土地売却・宅地転用 | 共有者全員の同意 |
💡例題で理解を深めよう!
例題1
A(18歳未満)が親の同意なくアパートを借りる契約をした。この契約の効力はどうなるか。
→ 答え:取り消すことができる(民法5条2項)
例題2
管理業者が貸主の代理で入居契約を締結する。この契約の性質は?
→ 答え:委任契約(貸主の代理として法律行為を行うため)
例題3
請負業者が修繕工事を完了したが、引渡し後に欠陥が判明した。注文者が1年経過後に修補を求めた。
→ 答え:権利消滅(637条1項)
例題4
共有建物を3年貸す契約を結ぶ場合の決定要件は?
→ 答え:共有者の持分の過半数で決定(252条4項)
まとめ:契約の「性質」と「行為能力」を軸に整理!
✅ 権利能力・意思能力がなければ契約は無効
✅ 未成年者や成年被後見人は保護の対象
✅ 管理受託契約=委任・準委任+請負の要素を併せ持つ
✅ 請負は「結果責任」、委任は「信頼関係」がポイント
✅ 賃貸借は不要式契約、借地借家法で賃借人保護
✅ 契約前の行為にも「契約締結上の過失」がある
おわりに
民法の「契約の性質と当事者能力」は、賃貸不動産経営管理士試験で毎年必ず出題されています。
特に「委任と請負の違い」や「制限行為能力者の分類」は、暗記ではなく仕組みの理解が大切です。
条文番号とセットで整理しておきましょう。

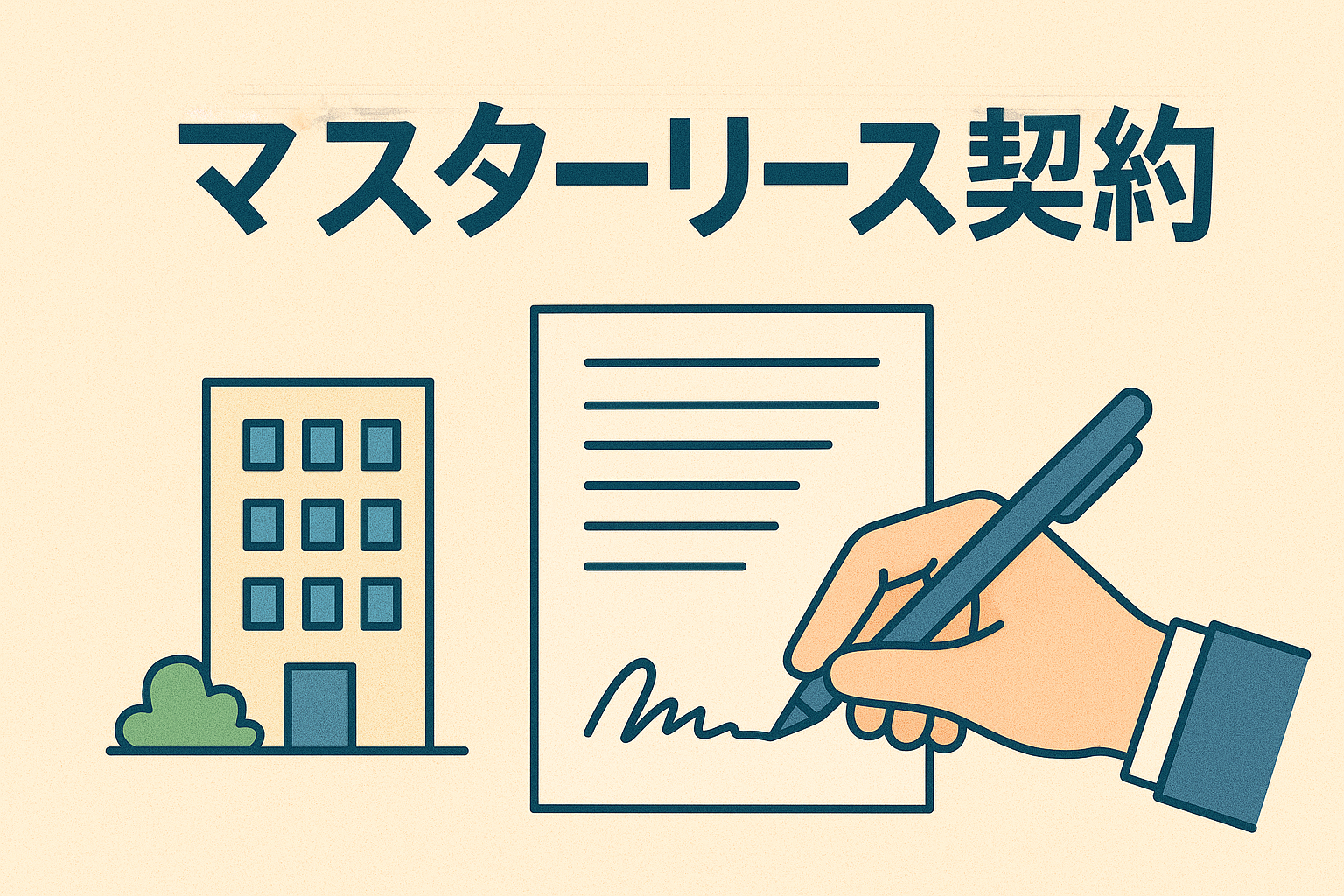
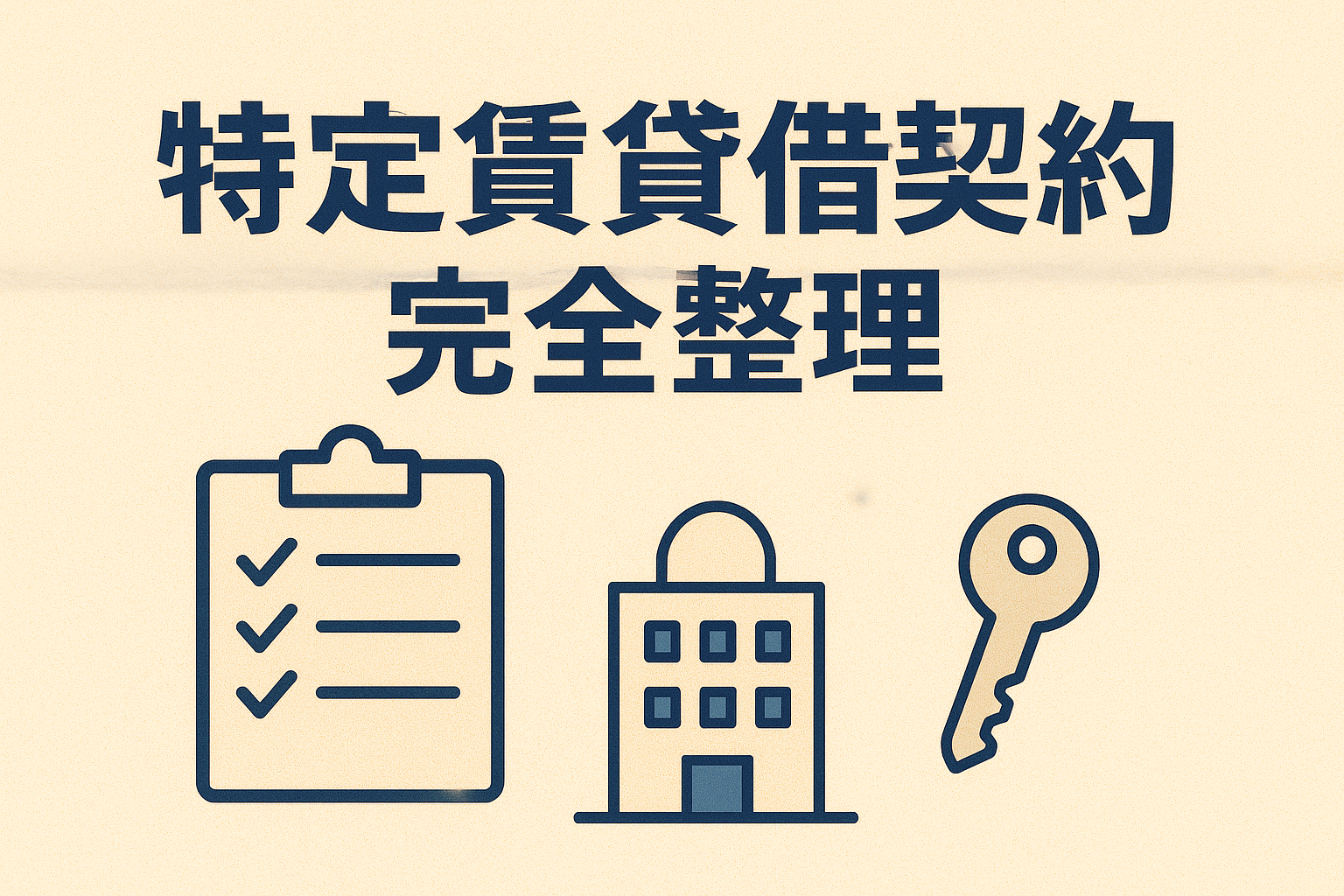
コメント