宅建試験の受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法で特に出題頻度の高い「重要事項説明」について、丁寧に解説します。
不動産取引では契約の前に、取引内容や物件の状況など、消費者が判断するための重要な情報を提供する義務があります。これが重要事項説明(35条)です。
宅建試験では、この重要事項説明に関するルールや、説明方法、説明者の資格などが頻出テーマとなっています。
本記事では、その基本ルールから説明方法、重要な35条書面、さらに例題までしっかり整理してお伝えします。
しっかり覚えて、得点源にしましょう!
重要事項説明の基本ルールとは
宅建業者は、不動産の売買・交換・貸借契約を締結する前に、取引の相手方(買主・借主)に対して、その物件や取引条件について、法律で定められた重要事項の説明を行う義務があります。
説明しなければならないのは、法律で「重要事項」と位置付けられている項目のみです。これに違反すると、宅建業法違反となり、行政処分や刑事罰の対象になります。
重要事項説明は、宅地・建物の売買、交換、貸借(媒介・代理含む)の取引形態を問わず、契約締結の前に必ず行わなければなりません。
重要事項説明の担当者は取引士だけ
この重要事項の説明は、宅地建物取引士(取引士)でなければ行えません。宅建業者の営業マンや事務職員が説明しても無効となります。
しかも、単に宅建試験に合格しているだけではなく、以下の条件も必要です。
- 取引士証の交付を受けていること
- 有効期間内であること
- 事務禁止処分を受けていないこと
つまり、「取引士証を携帯した取引士」だけが説明を行うことができます。
例題1
宅建業者A社の営業担当Bさん(宅建試験合格者・取引士証なし)が重要事項説明を行った。この場合の取扱いとして正しいものはどれか。
A. 宅建試験に合格していれば問題ない
B. 取引士証がなければ説明はできない
C. 社長の許可があれば説明可能
D. 代理で説明すれば問題ない
正解と解説
→B
取引士証を有効に交付されていない者は、説明を行うことはできません。
重要事項説明の方法と提示義務
重要事項説明は、「取引士証を提示したうえで、書面を交付して説明する」という手順で行います。
この流れは、宅建業法で厳格に決まっています。
- 宅地建物取引士証を提示する
- 重要事項説明書(35条書面)を交付する
- 内容を読み上げて説明する
- 取引士証の記名押印をする
この4ステップが必要です。特に、「口頭での説明」だけ、「書面だけの交付」は宅建業法違反です。必ずセットで行わなければなりません。
例題2
宅建業者C社が重要事項説明書を交付し、宅建士Dさんが取引士証の提示をせずに説明を行った。この場合、宅建業法上の取扱いとして正しいものはどれか。
A. 説明内容に誤りがなければ問題ない
B. 取引士証の提示は不要
C. 取引士証の提示がないと違反
D. 書面交付だけで説明は省略できる
正解と解説
→C
取引士証の提示は義務です。提示せずに説明を行うのは違反となります。
35条書面(重要事項説明書)の内容
35条書面には、宅建業法で定められた重要事項が記載されていなければなりません。
売買・交換・貸借で説明すべき内容は異なるため、内容をよく確認しておきましょう。
【売買・交換で必ず説明する内容】
- 登記記録に記録された権利の種類・内容
- 私道に関する負担
- 接道状況
- 建築基準法上の制限
- 代金支払方法・支払時期
- 手付金・違約金の額と返還方法
- 契約解除に関する事項
【貸借契約で必ず説明する内容】
- 登記記録に記録された権利の種類・内容
- 賃貸物件の用途制限
- 設備の整備状況
- 契約期間・更新条件
- 敷金・礼金の額と返還条件
この説明内容は試験によく出題されるため、表にまとめて暗記しておくのがおすすめです。
重要事項説明のタイミングと注意点
重要事項説明は、必ず「契約前」に行わなければなりません。契約締結後に説明を行った場合は、無効となり、場合によっては取消し原因ともなります。
また、以下の点も注意です。
- 購入希望者が説明を受けたがらなくても必須
- 賃貸でも必ず行う
- 重ねて契約行為とみなされる言動があれば、先に説明必須
例題3
宅建業者E社は、契約締結の直前に買主の希望で重要事項説明を省略した。この場合の取扱いは?
A. 買主が望んだなら省略可能
B. 書面交付のみなら可
C. 契約前なら必ず説明しなければならない
D. 契約後の説明でも有効
正解と解説
→C
契約締結前に必ず説明が必要で、買主の希望による省略も認められません。
宅建試験攻略のポイント
この重要事項説明の分野では、以下のポイントを押さえておきましょう。
- 取引士証の提示義務
- 口頭と書面交付のセット義務
- 売買・交換と貸借で説明内容の違い
- 重要事項説明のタイミング
- 試験頻出の35条書面の記載内容
例題形式で反復演習を繰り返し、覚えるより「使える」状態にしておくのが合格への近道です。
特に35条・37条(契約書面)との違いも併せて整理しておきましょう。
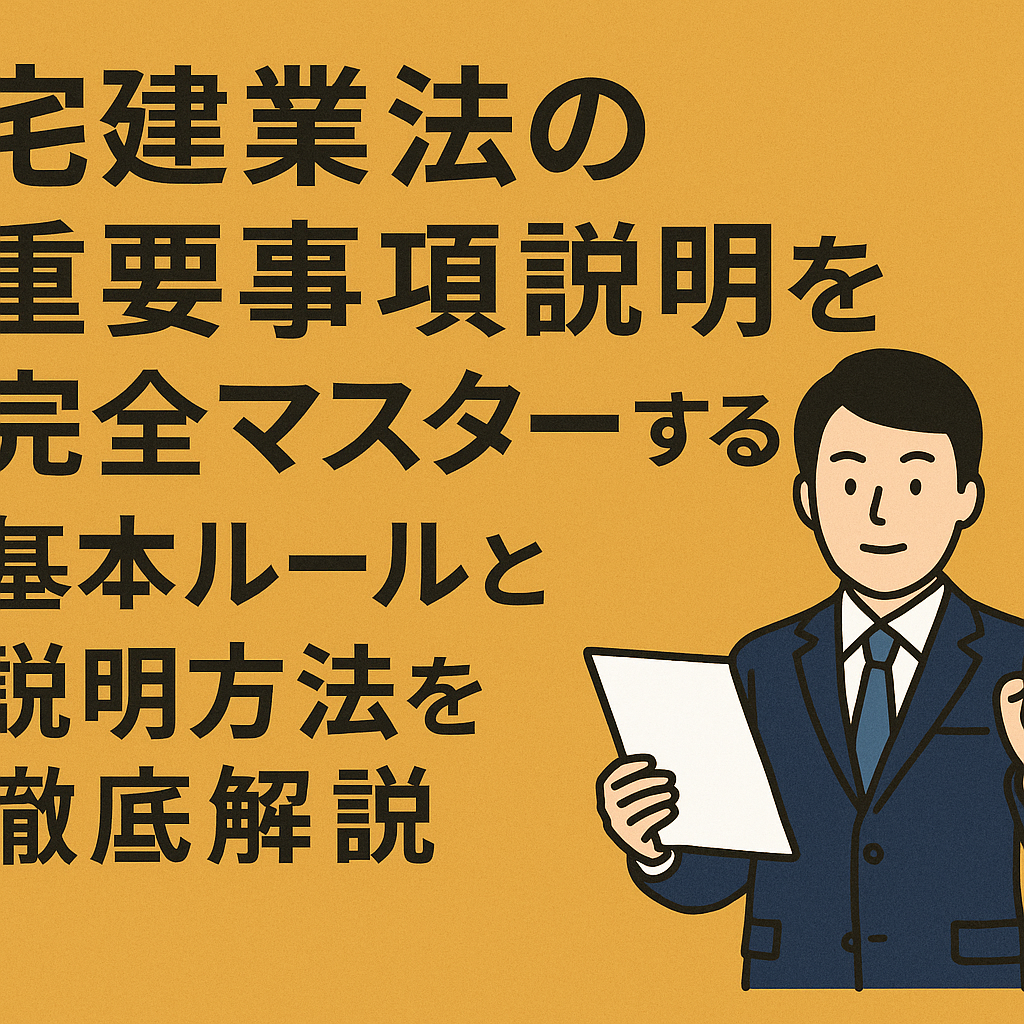
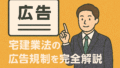
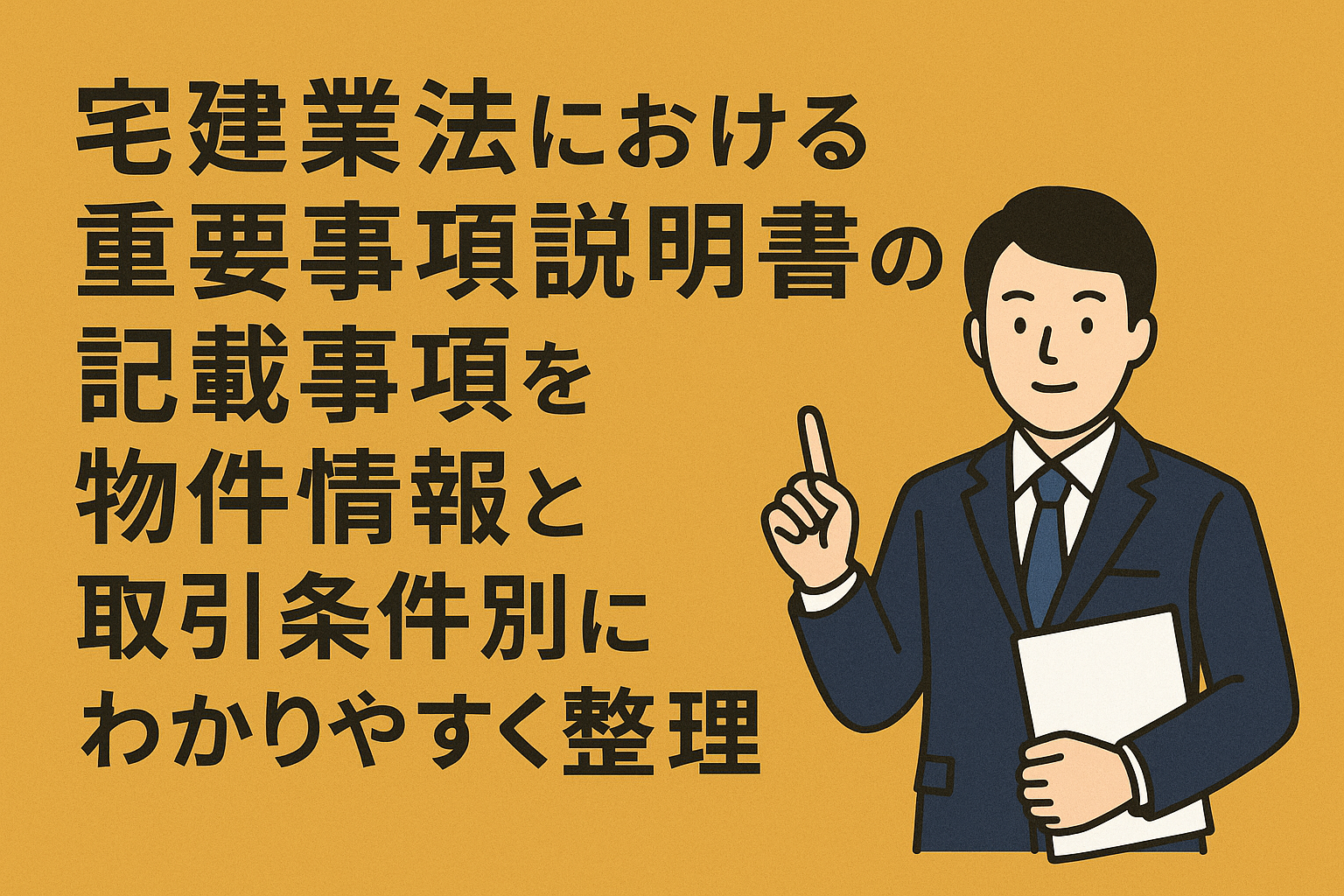
コメント