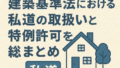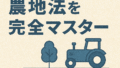建築基準法の「集団規定」は、建築物が密集する市街地において、まちづくりの秩序を保つために不可欠な規制です。今回は、その集団規定の中でも特に重要な「高さ制限」と「建築協定」について、宅建試験で頻出するポイントを丁寧に解説します。
複雑な斜線制限や日影規制、防火地域の建築制限はもちろん、住民が自ら住環境を守るために合意して定める「建築協定」のルールまで、試験対策に欠かせない知識を押さえていきましょう。
⸻
高さ制限の基本と絶対高さ制限
第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域には、「絶対高さ制限」と「外壁の後退距離制限」があります。
- 絶対高さ制限:都市計画で10mまたは12m以内と定められ、原則的にこれを超えては建築できません。
- 外壁の後退距離:都市計画で1mまたは1.5m以内とされ、敷地境界からこの距離以上は外壁を後退させなければなりません(ただし任意で定める)。
これらの制限は、低層住宅地域にふさわしい良好な住環境を維持するために必要な規制です。
⸻
3つの斜線制限とは?道路・隣地・北側の違いを理解
斜線制限とは、建築物が過度に高くならないよう、空間に仮想の「斜線」を設定し、その斜線を超えた建築ができないようにするものです。以下の3つがあります。
1. 道路斜線制限
前面道路の反対側から一定勾配の斜線を引き、それを超える建物は禁止。
- 住居系地域:1対1.25
- その他:1対1.5
原則としてすべての都市計画区域および準都市計画区域に適用されます。
2. 隣地斜線制限
隣地との境界から建物の高さ制限を設定。
- 住居系地域: 立ち上がり20m or 31m → 勾配1対1.25
- その他: 立ち上がり31m → 勾配1対2.5
※第一種・第二種低層住居専用地域および田園住居地域は適用除外です。
3. 北側斜線制限
敷地の北側の隣地に日照を確保するための制限。
- 第一種・第二種低層:5mから1対1.25
- 第一種・第二種中高層:10mから1対1.25
※ただし、日影規制が条例で定められている場合は北側斜線は適用されません。
⸻
日影規制と複合日影の考え方
日影規制は、建物が冬至の日の日照時間においても長時間影を落とすことがないよう定められています。対象区域は地方公共団体の条例で定められ、用途地域ごとに規制内容が異なります。
- 低層住居専用地域:軒高7m超または地上3階建て以上
- 準住居・近隣商業・準工業:高さ10m超の建物が対象
- 商業・工業・工業専用:原則対象外。ただし10m超かつ影が対象区域にかかる場合は規制あり
複合日影とは、敷地内に複数の建物がある場合、1つでも日影規制の対象となる建物があれば、他もまとめて規制対象とされることです。
⸻
防火地域・準防火地域での建築制限
防火・準防火地域は都市計画法で指定され、建築基準法では具体的な建築制限が課されます。
耐火建築物・準耐火建築物の基準
- 防火地域:3階以上または延べ面積100㎡超 → 耐火建築物
- 準防火地域:4階以上または1,500㎡超 → 耐火建築物、3階以下かつ500㎡~1,500㎡ → 準耐火建築物
また、延焼防止の観点から看板や塀、外壁・開口部にも規制があります。
⸻
建築協定とは?住民が自ら定める制限
建築協定とは、住民が合意のうえで建築基準法よりも厳しい制限を設ける制度です。
- 成立には土地所有者等の全員の合意が必要
- 合意後、特定行政庁の認可と公告で効力を持つ
- 協定は、将来的にその土地の所有者となる者にも拘束力がある
例えば、静かな住宅街にパチンコ店が建てられることを防ぐために、地域の住民が協定を結び、「特定の用途は禁止」と定めることができます。
⸻
一人協定とは?デベロッパー向けの特例制度
一人協定は、まだ土地の所有者が1人(例:開発業者)の段階で、将来にわたり一定の建築制限を課したい場合に利用できる制度です。
- 成立には特定行政庁の認可と公告が必要
- 効力は、認可後3年以内に所有者が2人以上になった時点から発生
⸻
例題で確認しよう!
問題:
北側斜線制限が適用される用途地域はどれか?
ア.商業地域
イ.第一種低層住居専用地域
ウ.準工業地域
エ.工業地域
正解:イ
→ 北側斜線制限は、第一種・第二種低層住居専用地域、田園住居地域、中高層住居専用地域に適用されます。ただし中高層地域では日影規制があると適用されません。
⸻
まとめ
建築基準法の集団規定と建築協定は、出題範囲が広く、数字や地域の違いによる適用可否が複雑なため、理解が不十分だとミスをしやすい分野です。
この記事で紹介した以下のポイントは、特に繰り返し確認しておきましょう。
- 絶対高さ制限と外壁後退距離の違い
- 斜線制限(道路・隣地・北側)の適用地域と勾配
- 日影規制の対象条件と条例指定区域の確認
- 防火・準防火地域での建築制限
- 建築協定・一人協定の成立要件と効力範囲
しっかり覚えて、得点源にしてください!