はじめに
サブリース契約(マスターリース契約)は、賃貸住宅管理業におけるトラブルが多い分野のひとつです。
実際、オーナーに対して「30年家賃保証」などと誤解を与える勧誘を行い、契約後に家賃減額や契約解除をめぐるトラブルが発生するケースが相次いでいます。
そこで国は、これらの問題を防止するために「賃貸住宅管理業法」において、特定賃貸借契約(マスターリース契約)と特定転貸事業者(サブリース業者)に関する規制を設けました。
今回はこの制度のポイントを、試験で問われやすい部分を中心に、例題を交えて解説します。
特定賃貸借契約とは? ― サブリース方式の核となる契約
「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅を第三者に転貸する事業を目的として結ばれる賃貸借契約のことです(賃貸住宅管理業法2条4項)。
この契約に基づき、賃貸住宅を借り上げて転貸事業を行う業者を「特定転貸事業者(サブリース業者)」と呼びます。
ただし、以下のような密接な関係にある場合は特定賃貸借契約から除外されます(施行規則2条)。
■除外される主なケース
- 賃貸人が個人で、相手方がその親族や親族が役員の法人の場合
- 賃貸人が会社で、その親会社・子会社・関連会社に貸す場合
- 投資法人の資産運用会社との契約
- 特定目的会社や不動産特定共同事業に関係する取引
これらは内部取引的な性格が強く、「一般オーナー保護を目的とする規制」の対象外となります。
特定賃貸借契約が対象となるかの判断ポイント
✅ 「事業として反復継続して転貸しているか」
単発的な一時転貸(たとえば転勤期間だけ自宅を貸す等)は該当しません。
営利目的で反復継続して行う場合のみ「事業」とみなされます。
✅ 再転貸の場合
サブリース業者が借り上げた物件をさらに別の業者が借り上げて再転貸する場合も、その間の契約も特定賃貸借契約とされます。
✅ 借上社宅の場合
企業が従業員に貸すために借上社宅を利用する場合、企業自身は営利目的ではないため、特定転貸事業者には該当しません。
ただし、社宅代行業者は手数料収益を得るため、特定転貸事業者に該当します。
サブリース業者と勧誘者への主な規制(5つの柱)
賃貸住宅管理業法では、サブリース事業に関する誤認防止のため、次のような5つの規制を設けています。
| 規制内容 | 該当条文 |
|---|---|
| ① 誇大広告等の禁止 | 第28条 |
| ② 不当な勧誘等の禁止 | 第29条 |
| ③ 重要事項説明義務(契約前) | 第30条 |
| ④ 契約締結時書面の交付義務 | 第31条 |
| ⑤ 書類の閲覧義務 | 第32条 |
さらに、勧誘を行う者(建設会社・販売会社など)にも、誇大広告や不当勧誘の禁止が適用されます。
誇大広告等の禁止(第28条)
■禁止される表示
サブリース業者や勧誘者は、以下のような虚偽や誇張を含む広告表示をしてはいけません。
- 実際には家賃見直しがあるのに「○年家賃保証」と表示
- 契約期間中でも解約可能なのに「30年間借り上げ保証」などと断定
- オーナーの修繕負担があるのに「修繕費ゼロ」と誤解させる表示
- 「利回り○%保証」など、利益を確実に得られるような断定的表示
💡注意すべき広告の表現
「家賃保証」「空室保証」などの文言を使用する場合は、減額リスクや見直し時期を明示する必要があります。
また、強調表示(大きな文字・色付き)でメリットを強調し、リスク情報を小さく記載するような広告も違法とされることがあります。
📱媒体を問わず適用
チラシ・パンフレット・新聞・Webサイト・SNS・動画広告など、あらゆる広告媒体が対象です。
不当な勧誘等の禁止(第29条)
(1) 事実の不告知・不実告知の禁止
勧誘時に以下のような行為をすることは禁止されています。
- 家賃減額リスクを説明せず「家賃は下がらない」と伝える
- 「原状回復費はすべて業者負担」と虚偽の説明をする
- 「いつでも自由に解約できる」と誤解を与える
- 修繕義務があるにもかかわらず「修繕費ゼロ」と説明する
これらは「オーナーの判断に影響を与える重要事項」に該当し、虚偽説明をした場合には罰則の対象になります。
(2) 相手方の保護に欠ける行為の禁止
国交省令43条により、次のような勧誘行為も禁止されています。
- 夜9時以降や早朝の電話・訪問勧誘
- 長時間の勧誘で相手を困惑させる
- 「契約しないと帰さない」などの威迫行為
- 契約拒否の意思を示した相手への再勧誘
これらは「罰則」はありませんが、業務停止処分等の行政指導の対象となります。
勧誘者(サブリース業者以外)への適用範囲
建設会社・販売会社・金融機関などがサブリース契約を勧める場合、それが特定転貸事業者の依頼・委託に基づくものであれば、「勧誘者」として規制の対象になります。
該当する具体例
- 建設会社が建築提案時に特定業者のサブリース契約を紹介
- 不動産販売会社が物件購入時にサブリース契約を勧める
- サブリース会社から紹介料を受け取って勧誘を行う
このような行為は**「明示的な委託がなくても」**依頼関係があれば該当します。
学習のポイント整理
| 規制項目 | 内容の要点 | 試験での狙われ方 |
|---|---|---|
| 誇大広告等の禁止 | 虚偽・誇張・誤認広告は禁止 | 「○年保証」「利回り○%」などの誤表示例を問う |
| 不当な勧誘等の禁止 | 事実不告知・虚偽説明の禁止 | 「家賃下がらない」等の虚偽説明例を選ぶ |
| 再勧誘禁止 | 契約拒否後の勧誘もNG | 電話勧誘時間帯(9時〜8時)は要注意 |
| 勧誘者の定義 | 特定業者の依頼で勧誘する者 | 委託関係がなくても該当する場合あり |
💡例題で理解を深めよう!
例題1
サブリース業者Aが、オーナーBに対して「家賃は30年間一切下がりません」と説明し契約を締結したが、実際には2年ごとに家賃見直し条項があった。
この行為はどの条文に違反するか?
答え:第28条(誇大広告等の禁止)
→ 実際よりも有利であると誤認させる表示に該当します。
例題2
建設会社Cが、自社のグループ会社D(サブリース業者)との契約をオーナーに勧める際、「契約しないと建築工事ができません」と強引に勧誘した。
この行為はどの規定に違反するか?
答え:第29条2号・国交省令43条(威迫行為)
→ 契約締結を強要するような勧誘行為は禁止されています。
例題3
サブリース会社Eが、「修繕費も原状回復費も全て当社負担」と説明して契約を締結したが、契約書にはオーナー負担の記載があった。
この行為はどの規制に違反するか?
答え:第29条1号(不実告知)
→ 実際と異なる説明を行う行為にあたり、罰則対象です。
まとめ:試験・実務に直結する重要論点
✅ 「特定賃貸借契約」はサブリース契約の法的名称
✅ サブリース業者=「特定転貸事業者」
✅ 誇大広告・不当勧誘は試験でも出題頻度が高い
✅ 広告表現(「○年保証」「利回り」等)のリスク表示が鍵
✅ 不実告知・事実不告知には罰則あり(42条2号)
おわりに
サブリース契約に関する法規制は、オーナー保護の観点から非常に重要な分野です。
賃貸不動産経営管理士試験でも、「誇大広告等の禁止」や「不当な勧誘等の禁止」を中心に毎年出題されています。
本記事の例題と整理表を繰り返し確認し、**「条文の番号・趣旨・具体例」**をセットで覚えるようにしましょう。
次回は「特定賃貸借契約の重要事項説明書と締結時書面の内容」について詳しく解説します。
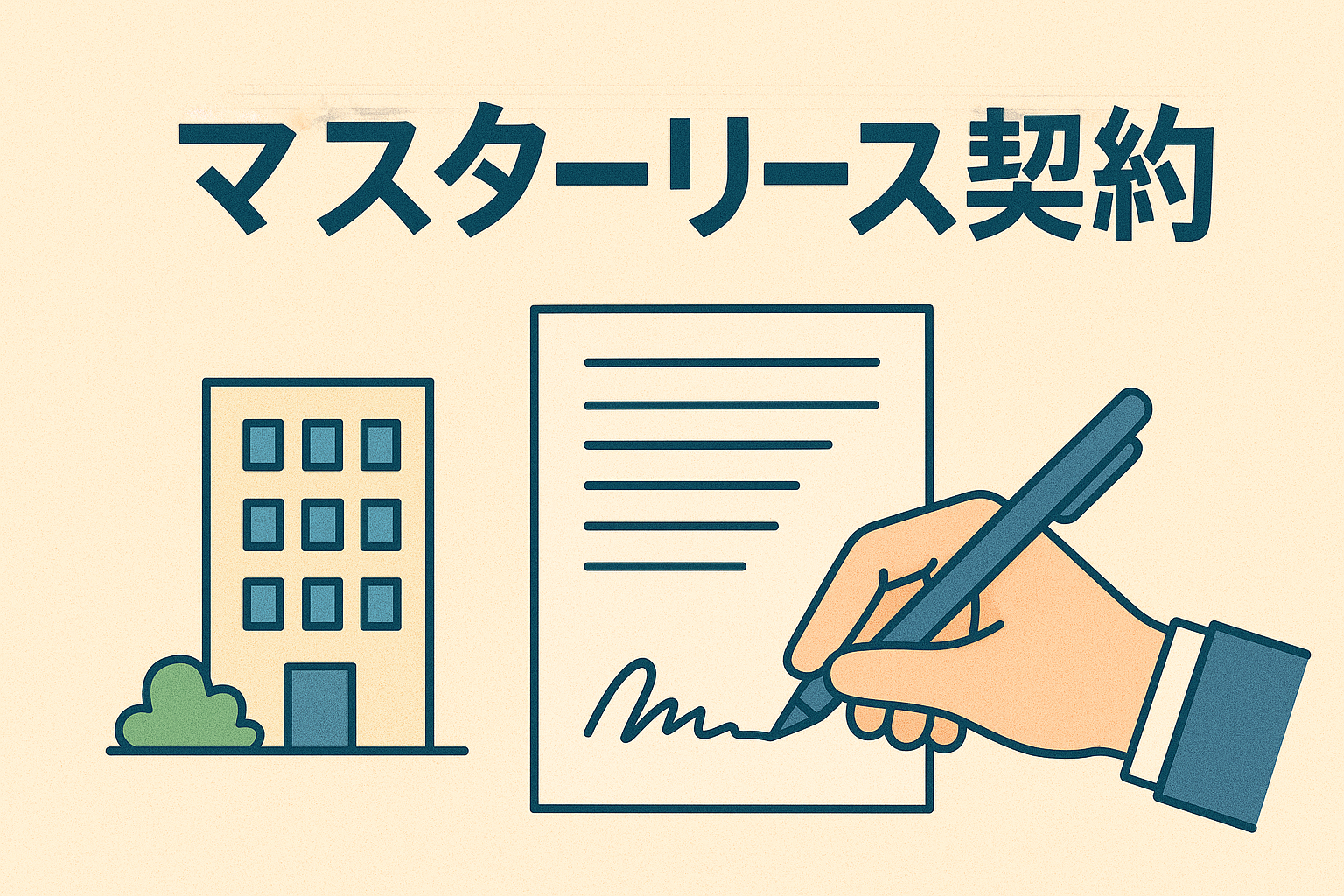


コメント