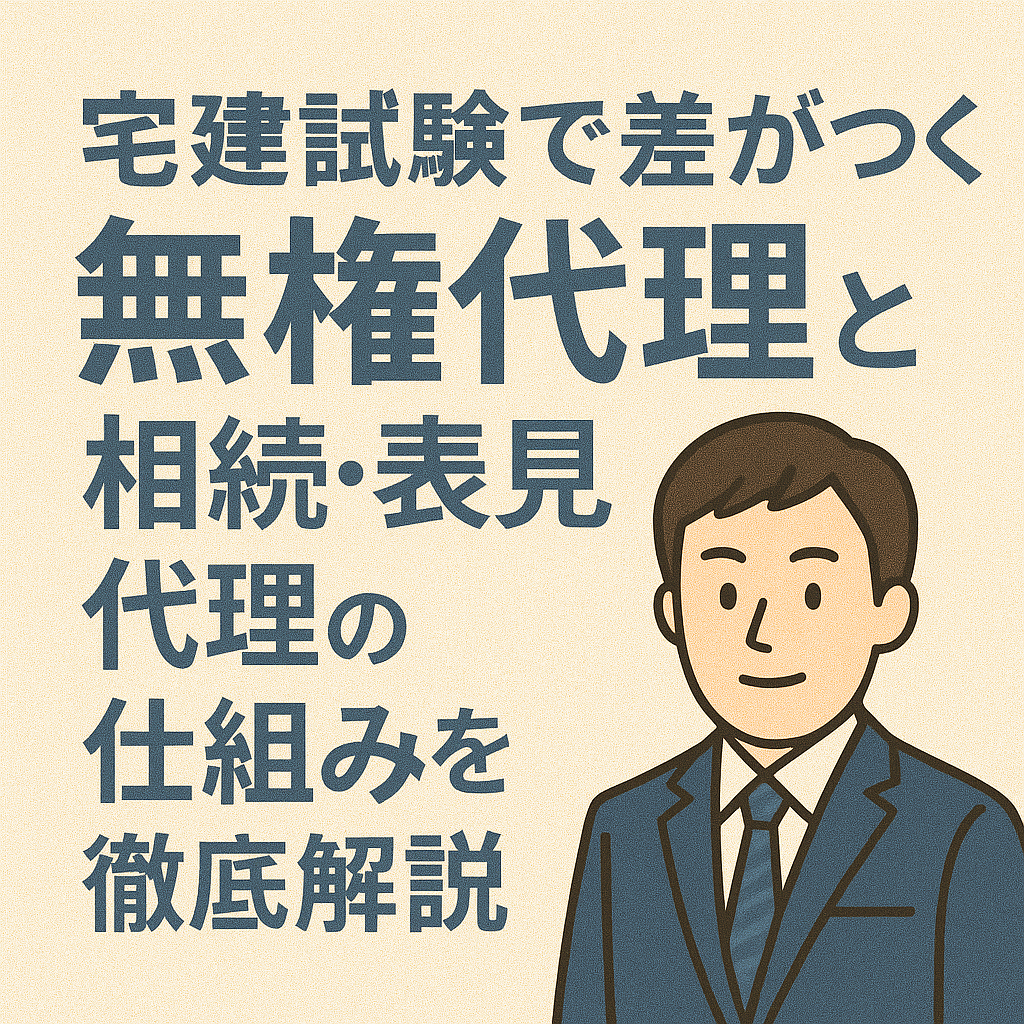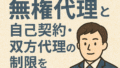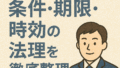宅建試験において「代理」の分野は定番の出題テーマですが、中でも「無権代理と相続」「表見代理」に関する設問は、判例の理解が問われ、正答率に差が出やすい内容です。
この記事では、無権代理人が本人を相続した場合やその逆のパターン、さらに表見代理の三つの類型と重畳適用について、具体例と例題を交えて丁寧に解説します。
⸻
無権代理と相続の5つのパターンを押さえよう
① 無権代理人が本人を単独相続した場合
無権代理人が本人を単独相続した場合、追認拒絶はできません。
例:子Bが父Aの無権代理行為をし、Aの死後Bが単独相続した場合、判例は信義則上、追認拒絶を認めないとしています。
② 本人の追認拒絶後に無権代理人が本人を単独相続した場合
本人が生前に追認拒絶した後に、無権代理人がその本人を相続した場合、その追認拒絶の効果が優先され、有効にはなりません。
③ 無権代理人が本人を共同相続した場合
他の相続人と共同で相続した場合、全員が共同して追認しなければ、無権代理行為は有効になりません。
判例は「無権代理人の相続分に対応する部分においても当然に有効とはならない」としています。
④ 本人が無権代理人を相続した場合
この場合、本人が追認を拒絶しても信義則に反しないため、無権代理行為は当然には有効になりません。
ただし、無権代理人が相手方に債務を負っていた場合は、その債務から免れることはできません。
⑤ 本人と無権代理人の双方を相続した者がさらに本人を相続した場合
この複雑なケースでも、判例は「本人が自ら行為したのと同様の効果を生じる」とし、追認拒絶はできないとしています。
⸻
表見代理とは?無権代理でも効果が本人に及ぶ例外
表見代理とは、本来代理権がないにもかかわらず、外観上代理権があるように見える場合に、本人に効果を帰属させる制度です。
民法が定める表見代理には、以下の3つの法定類型があります。
⸻
① 代理権授与表示による表見代理(民法109条)
本人が実際には代理権を与えていないのに、与えたような表示を相手方に行った場合、善意・無過失の第三者を保護します。
例:Aが「Bに土地売却の代理権を与えた」とCに伝えたが、実際には代理権を与えていなかった。このときCが善意・無過失であれば、Aは履行責任を負います。
※法定代理(親権者や成年後見人)には適用されません。
⸻
② 権限外の行為の表見代理(民法110条)
代理人が与えられた権限を超えて行為したが、第三者に「正当な理由」があるときは、本人に効果が帰属します。
例:賃貸の代理権しかないBが、土地を売却した。Cが正当な理由(=善意・無過失)で信じた場合、売買契約は有効となり、Aは履行責任を負います。
⸻
③ 代理権消滅後の表見代理(民法112条)
かつて代理権があった者が、その代理権消滅後に旧代理権の範囲内で行為した場合、相手方が善意・無過失であれば、本人に効果が帰属します。
例:Bが以前はAの代理人だったが、代理権が消滅した後にA名義で契約を締結。Cがその消滅を知らず無過失であれば、Aに履行義務が発生します。
⸻
表見代理の重畳適用も理解しよう
重畳適用とは、複数の表見代理の類型が同時に成立する場合でも、それぞれの条文が併存的に適用されることです。
例:
- 表示された代理権の範囲を超えて行った場合 →「代理権授与表示+権限外の行為」
- 代理権消滅後に、権限を超えて行った場合 →「代理権消滅+権限外の行為」
このようなケースでも、相手方が善意・無過失であれば保護されます。
⸻
例題で知識を定着させよう
問題1: 無権代理人が本人を単独相続した場合、どうなるか?
ア.追認を拒絶できる
イ.無権代理行為は自動的に無効
ウ.追認を拒絶できない
エ.第三者の同意があれば有効となる
正解:ウ
→ 単独相続した無権代理人は信義則上、追認を拒絶できません。
問題2: 代理権授与表示による表見代理が成立するための要件に含まれないものはどれか?
ア.本人の表示
イ.第三者の善意
ウ.第三者の無過失
エ.法定代理人による表示
正解:エ
→ 法定代理には代理権授与表示による表見代理は適用されません(判例)。
⸻
問題3: 表見代理の成立に必要な相手方の状態として正しいものは?
ア.善意のみでよい
イ.無過失のみでよい
ウ.善意かつ無過失
エ.悪意であってもよい
正解:ウ
→ 相手方が「善意かつ無過失」であることが必要です。
⸻
まとめ
宅建試験で出題される無権代理と表見代理に関しては、以下の点を確実に押さえましょう。
- 相続によって無権代理行為が有効になるかどうかは、相続の方向と追認の有無による
- 表見代理には3類型があり、それぞれ善意・無過失の第三者保護が要件
- 条文の併用が可能な「重畳適用」もある
- 判例知識が問われるため、例とセットで覚えることが重要