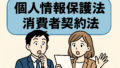宅建試験の合格を目指す皆さん、こんにちは。
試験まで1ヶ月を切り、最後の追い込みに励んでいることと思います。今回は、不動産市場のリアルな動向を示す「マンション賃料インデックス」の最新データについて解説します。昨日9月22日に発表された2025年第2四半期(4~6月)のデータによると、東京23区の賃料は、シングルからファミリー向けまで、全てのタイプで上昇しました。しかしその一方で、首都圏の郊外や大阪市など、一部のエリアでは下落も見られ、市場の「二極化」が鮮明になっています。この背景を理解することは、プロとして市場を読み解く上で不可欠です。
全面積帯で上昇 東京23区の圧倒的な強さ
まず、今回の調査で最も注目すべきは、東京23区の圧倒的な強さです。シングル向け(18~30㎡)、コンパクト向け(30~60㎡)、ファミリー向け(60~100㎡)の全ての面積帯で賃料指数が上昇しました。特に、ファミリータイプの賃料は前期比で+3.17ポイントと力強い伸びを見せており、幅広い層で賃貸需要が非常に旺盛であることがわかります。
なぜ23区の賃料は上がり続けるのか?
では、なぜ東京23区の賃料はこれほどまでに上昇を続けているのでしょうか。その背景には、複数の要因が複雑に絡み合っています。
- 都心回帰の本格化
コロナ禍で一時的に進んだ郊外移転の流れが終わり、企業への出社が常態化したことで、通勤・通学に便利な都心部に住みたいという需要が再燃しています。 - 新築賃貸物件の供給不足
建築費や人件費の高騰により、デベロッパーが新しい賃貸マンションの建設に慎重になっています。需要が増加する一方で、供給が追いついていないため、既存物件の希少価値が高まり、賃料を押し上げています。 - 物価上昇の影響
物価全体が上昇する中で、マンションの管理費や修繕費といった運営コストも増加しています。オーナー(貸主)が、これらのコスト増を賃料に転嫁する動きも出始めています。
一方で下落も…首都圏郊外・大阪の状況
23区が力強い上昇を見せる一方で、東京都下(多摩地域)や千葉県西部、大阪市などでは、賃料指数が前期比で下落しました。この背景には、それぞれの地域の事情があります。例えば、大阪市では単身者向け物件の供給が豊富で、交通網も発達しているため、都心に固執しなくても利便性の高い物件を見つけやすい環境があります。これにより、エリア内で価格競争が起き、賃料が安定、あるいは下落する傾向が見られます。
「賃料インデックス」から読み解く市場の二極化
この一連のデータが示すのは、賃貸市場の鮮明な「二極化」です。利便性や希少性の高い東京23区に需要が集中して賃料が上昇する一方、郊外や他の大都市では、供給量や価格の妥当性がシビアに評価され、賃料が伸び悩んだり下落したりしています。もはや、「首都圏」「大都市」と一括りにして市場を語ることはできず、エリアごとのミクロな分析が不可欠な時代になっているのです。
宅建士に必須の「賃料査定」と「市場説明」の能力
私たち宅建士を目指す者にとって、このニュースは非常に重要な示唆を与えてくれます。賃貸仲介における宅建士の重要な業務の一つが「賃料査定」です。そして、査定した賃料の根拠を、貸主と借主の双方に納得してもらえるよう説明する「市場説明」の能力が求められます。
例えば、貸主に対しては、「23区では市場が強いので強気の賃料設定も可能ですが、多摩地域では近隣の供給状況を考えると、少し抑えた方が早く客付けできるかもしれません」といった、データに基づいた具体的な提案が必要になります。
また、借主に対しては、「このエリアの家賃が高いのは、こういう背景があるからです」と、市場の状況を丁寧に説明することで、納得感を持って契約してもらうことができます。
試験で学ぶ「借地借家法」の知識はもちろんですが、こうしたリアルタイムの市場動向を常に把握し、データに基づいて論理的な説明ができること。それこそが、AIには真似のできない、信頼される不動産のプロフェッショナルへの道なのです。