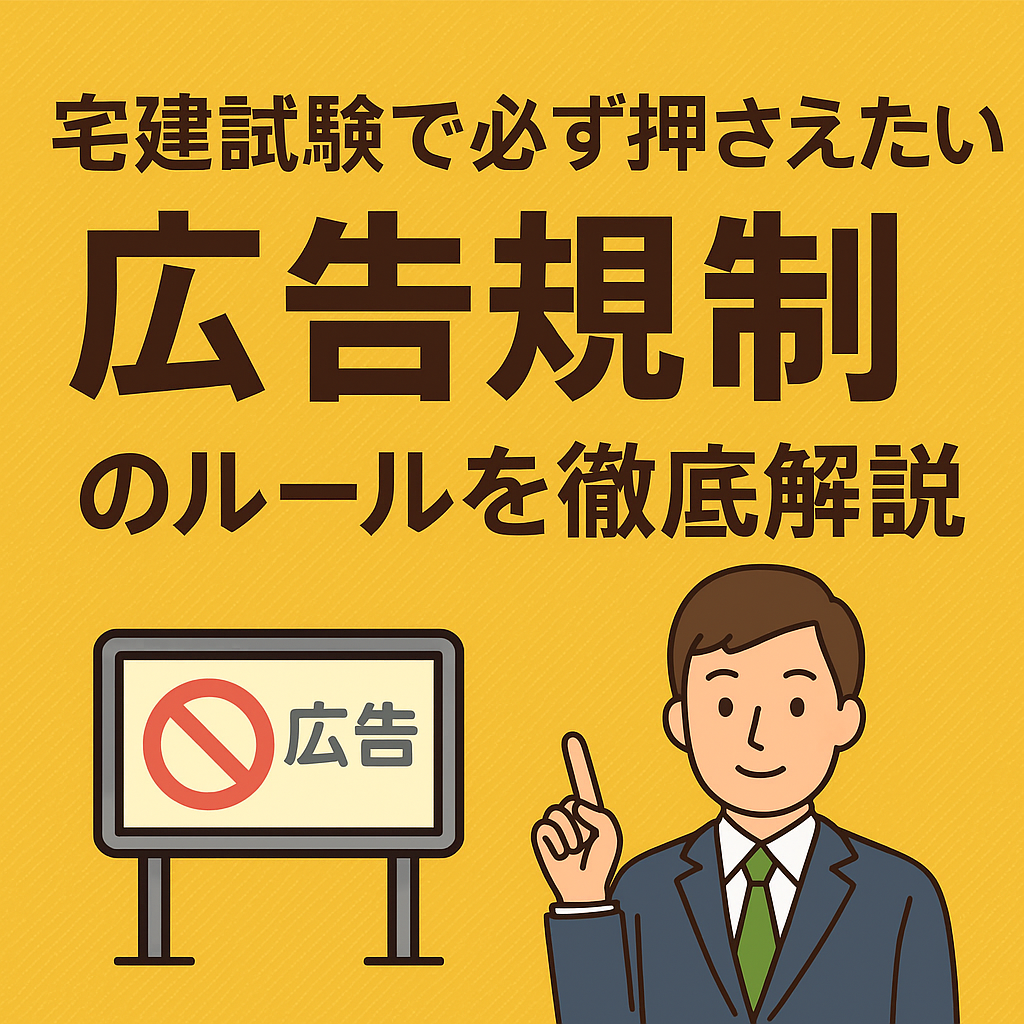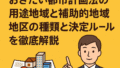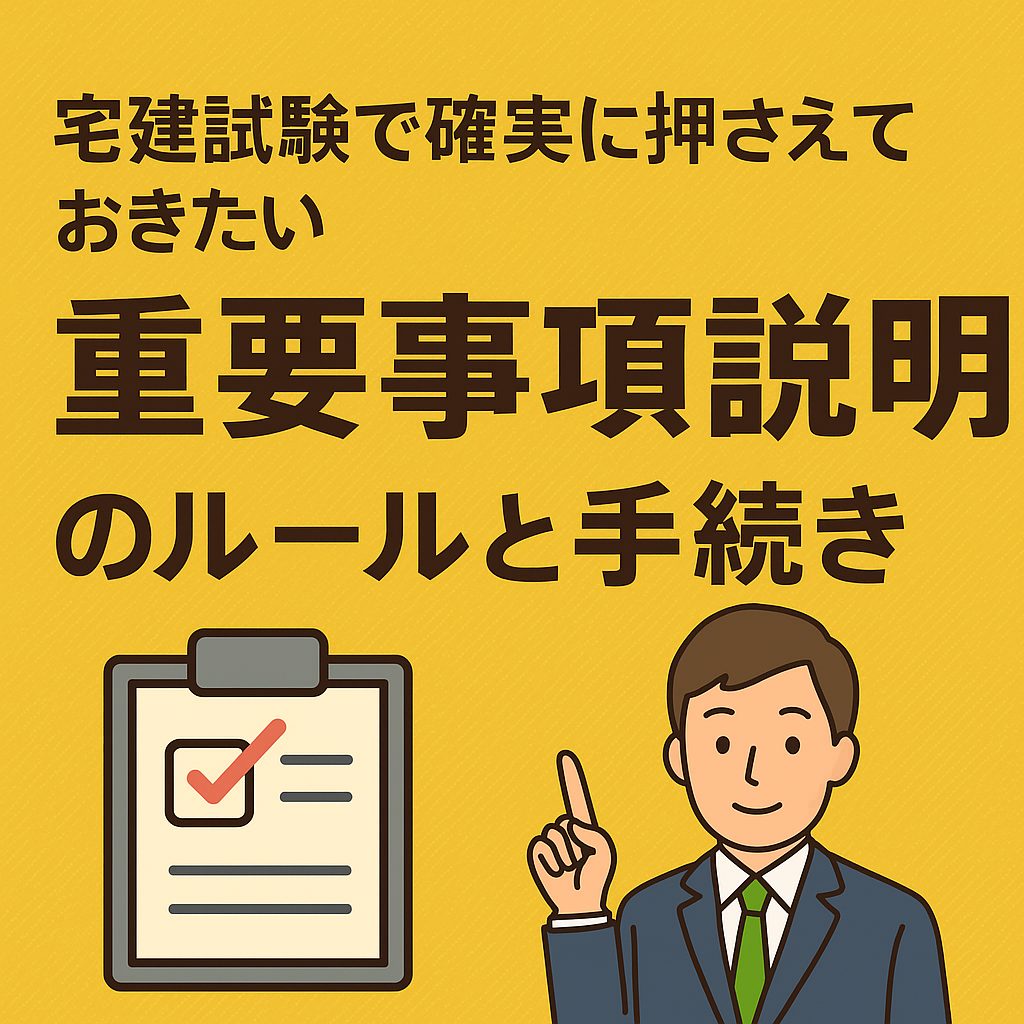宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
今回は宅建業法の中でも出題頻度が高い「広告規制」について詳しく解説します。
誇大広告の禁止、広告開始の制限、取引態様の明示は、実務でも試験でも非常に重要な内容です。
この記事では、例題も交えながら分かりやすく整理しましたので、しっかり得点源にしていきましょう。
⸻
誇大広告等の禁止とは
宅建業者が行う広告には、誇大広告等を行ってはならないという決まりがあります。
著しく事実と異なる表示や、実際よりも著しく優良・有利に見せかける表示は法律違反です。
誇大広告に該当する例としては次のようなものがあります。
- 実在しない物件を広告する(おとり広告)
- 取引の意思がない物件を表示する
- 実際より著しく利便性が高い、環境が良いと誤認させる表示
このような誇大広告を行った場合、被害の有無にかかわらず違反となり、監督処分・懲役または罰金刑が科せられることがあります。
誇大広告の対象となる項目
1. 物件の所在
2. 規模(敷地面積・床面積)
3. 形質(構造・種類)
4. 利用の制限
5. 周囲の環境
6. 交通の利便性
7. 代金・借賃・支払方法
8. 金銭の貸借のあっせん
例題1
広告に記載する内容として宅建業法違反となるものはどれか。
A. 実際に売却する意思のない物件
B. 建物の正しい面積
C. 実際の取引価格
D. 交通機関の正しい所要時間
正解 → A
意思のない物件を広告するのは「おとり広告」で、誇大広告に該当します。
⸻
おとり広告とは
おとり広告は、誇大広告の一種で、次のようなものがあります。
1. 物件が存在しない
2. 取引できない
3. 取引の意思がない
いずれも宅建業法違反となりますので、試験でも頻出ポイントです。
⸻
広告の開始時期の制限
未完成物件の場合、開発許可や建築確認などの法令による許可・確認を受けた後でなければ広告できません。
「申請中」や「確認待ち」の状態では広告はできず、例えば「建築確認申請中、確認後に契約可能」と表記しても違反です。
売買・交換・貸借いずれの取引も、この制限が適用されます。
例題2
建築確認の申請中の物件について「確認後に契約可能」と注記して広告を行うことはできるか。
A. できる
B. できない
正解 → B
建築確認が下りるまでは、注記しても広告はできません。
⸻
変更確認の取扱い
建築確認を受けた後、計画変更のため「変更確認」を申請する場合には、以下の取扱いが必要です。
① 当初確認内容での広告継続は可能
② 変更確認の申請中でも、「変更確認の予定」である旨と当初の内容を明記すれば、変更後の内容も広告可能
③ スケルトン・インフィル工法のマンションの場合は「具体的な間取り確定後に変更確認が必要となる場合もあります」と明記すれば広告可
⸻
取引態様の明示義務
取引態様とは、「自ら売主」「代理」「媒介」などの取引形態のこと。
宅建業者は広告をするとき、さらに注文を受けたときにも遅滞なく取引態様を明示しなければなりません。
広告で明示したからといって、注文時に省略することはできません。
注文を受けたときにも、口頭でも構わないので必ず明示する義務があります。
例題3
宅建業者が広告で取引態様を明示し、来店した客が注文したときの取扱いとして正しいものはどれか。
A. 注文時には再度の明示は不要
B. 口頭であっても注文時に明示する
C. 広告で明示していれば省略可能
D. 契約締結時のみ明示すればよい
正解 → B
注文時にも口頭で取引態様を明示する必要があります。
⸻
試験対策まとめとポイント
広告規制の分野では、以下のポイントを押さえましょう。
- 誇大広告禁止(著しく事実と異なる・誤認させる表示)
- おとり広告(存在しない・取引不可・意思なし)
- 広告開始時期(許可・確認後でなければ不可)
- 変更確認の取扱い(当初確認の内容で広告継続可、変更予定も明記要)
- 取引態様の明示(広告時・注文時の両方で必須、口頭可)
これらは毎年必ずといっていいほど問われる範囲なので、過去問演習と例題でしっかり押さえておきましょう。