宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
本記事では宅建業法の中でも出題頻度が高く、理解が難しいとされる「営業保証金制度」について、試験で問われる要点をしっかり押さえながら、分かりやすく丁寧に解説していきます。
さらに例題も豊富にご用意しましたので、読みながら実践力も同時に身につけましょう。
宅建試験の合格を目指すなら、この営業保証金制度は絶対に避けて通れない重要分野です。
営業保証金制度とは何か
営業保証金制度とは、不動産取引に関わる消費者を保護するため、宅建業者が営業開始前に、法務局の供託所に一定額の保証金を供託することを義務付けた制度のことです。
この保証金は、万が一宅建業者が倒産したり、売買代金の支払いを怠ったりした場合に、取引の相手方である消費者の損害を補償するための資金として活用されます。
なぜ営業保証金制度が必要なのか
不動産取引は高額な金銭が動く取引であり、宅建業者が万が一支払不能や経営破綻に陥ると、取引の相手方である消費者に甚大な損害が発生します。
例えば、顧客が宅建業者に不動産を売却したものの、代金が支払われない場合。
こうしたリスクから消費者を守るために、この営業保証金制度が存在するのです。
宅建業法では、この制度によって宅建業者が一定の財産的基礎を持ち、不測の事態が発生しても消費者の利益が守られるようにしています。
営業保証金の供託金額
営業保証金の供託金額は、宅建業者の事務所の数によって次のように定められています。
- 本店(主たる事務所):1,000万円
- 支店(その他の事務所):1店舗につき500万円
例えば、本店+2支店を有する宅建業者の場合、以下のように計算されます。
1,000万円(本店)+500万円×2=2,000万円
この金額を主たる事務所の最寄りの供託所にまとめて供託する必要があります。
供託の場所と方法
営業保証金は、必ず本店(主たる事務所)の最寄りの法務局の供託所に供託します。
たとえ支店が他府県にあっても、本店の最寄りの供託所に全額まとめて供託する点に注意が必要です。
供託は、金銭のみならず、有価証券を利用することも可能です。
金銭以外の供託(有価証券の評価額)
有価証券による供託も認められており、国債・地方債など、一定の証券に限られます。評価額は以下の通りです。
- 国債:額面の100%
- 地方債・政府保証債:額面の90%
- その他一定の有価証券:額面の80%
例えば、国債500万円分を供託すれば、評価額も500万円ですが、地方債なら450万円、その他の証券なら400万円として評価されます。
供託後の届出と免許取消しリスク
宅建業者は営業保証金を供託しただけでは営業開始できません。必ず供託後、免許権者(都道府県知事または国土交通大臣)にその旨を届出る必要があります。
免許日から3ヶ月以内に届出がない場合、免許権者は催告を行い、さらに1ヶ月以内に届出しないと免許の取消し(任意的取消し)の対象となります。
営業保証金の取戻し
宅建業者は、次のような場合に営業保証金の取戻しができます。
- 免許の失効・取消・廃業
- 保証協会へ加入(営業保証金制度から弁済業務保証金制度へ切替)
- 本店移転や事務所廃止による保証金過不足の調整
取戻しには、原則6ヶ月以上の公告期間を設け、還付請求者の有無を確認する必要があります。
営業保証金の還付の対象
還付の対象となるのは、宅建業に関する取引で発生した債権のみです。
たとえば以下のようなものです。
- 売買代金の未払債権
- 損害賠償請求権(債務不履行や不法行為)
逆に、以下は対象外となります。
- 広告費、広告料の債権
- 内装工事代金の債権
- 従業員の給与債権
還付請求の流れ
- 顧客が供託所へ還付請求
- 供託所が還付実施
- 免許権者に還付報告
- 免許権者から宅建業者に通知
- 宅建業者は不足分を新たに供託し、届出
このとき、宅建業者は通知を受けた日から2週間以内に不足分を供託し、さらに供託した日から2週間以内に免許権者に届出をしなければなりません。
試験でよくあるひっかけ問題:「還付を受けた日から2週間以内」→✖️ 「通知を受けた日から2週間以内」→〇
はい、承知しました!
では先ほどの【記事1】の続きを、このまま長文化・超詳解・例題付きで進めていきます。
今回もWordPressのビジュアル表示用形式でコピペOKです。
営業保証金の還付事例と具体例
ここでは、実際に営業保証金の還付が行われる場面を、より具体的に考えてみましょう。
例えば、宅建業者A社が倒産し、顧客であるBさんが売買代金500万円を受け取れない場合、Bさんは法務局の供託所に還付を請求することができます。
このとき、供託所は営業保証金の中からBさんへ500万円を還付します。
そして、供託所はその還付の事実を免許権者に通知し、免許権者はその宅建業者A社に対し「不足額を供託しなさい」と通知します。
宅建業者A社は、この通知を受け取った日から2週間以内に、不足分を供託し、その日から2週間以内に届出を行わなければなりません。
もしこれに従わないと、営業停止や免許取消の処分対象となります。
還付の限度額について
営業保証金から還付を受けることができる金額には、限度額があります。
これは、宅建業者が供託した金額を超えて還付することはできないという仕組みです。
例えば、本店+1支店の宅建業者で、供託額が1,500万円の場合、その1,500万円が還付の限度額となります。
もし複数の債権者がいる場合は、この中で按分して支払われます。
事務所の廃止・移転による営業保証金の変動
宅建業者が事務所の廃止や移転を行った場合、営業保証金の額が変わることがあります。
例えば、支店を1つ廃止した場合、その支店分の500万円を供託所から取り戻すことができます。
逆に、新たに支店を設置した場合は、開設後2週間以内に500万円を供託し、さらにその供託を免許権者に届出なければなりません。
注意点
- 支店の廃止→取り戻しには官報公告が必要
- 新設→2週間以内に供託
これも試験ではよく問われるので、期限と手続きの流れは必ず覚えましょう。
例題で確認しよう(演習問題)
例題3
宅建業者A社は、営業保証金制度により1,000万円を供託して営業を開始しました。その後、新たに支店を開設しました。この場合、A社がとるべき対応として正しいのは次のうちどれか。
A. 支店開設前に500万円供託し、届出る
B. 支店開設後1週間以内に500万円供託し、届出る
C. 支店開設後2週間以内に500万円供託し、届出る
D. 支店開設後3ヶ月以内に500万円供託し、届出る
正解と解説
→C
支店開設後「2週間以内」に、その支店分500万円を供託し、さらにその旨を免許権者に届出る必要があります。営業保証金制度では、支店開設後に供託するのが正しい手順です。営業保証金制度と弁済業務保証金制度でこの順番が異なるので注意。
営業保証金の保管替え
本店の移転によって主たる事務所の所在地が変わると、営業保証金の供託先も変更しなければなりません。これを「保管替え」と呼びます。
具体的には、新しい本店所在地の最寄りの供託所へ供託し直し、古い供託所からは取り戻しを行います。
この場合も、取り戻しには公告(6ヶ月以上)が必要になります。
※支店廃止時と同様、公告を怠ると還付請求権者の権利が奪われてしまうため。
手順のポイント
- 新しい供託所へ供託
- 供託した旨を免許権者に届出
- 古い供託所の保証金を公告(6ヶ月)後、取り戻し
よく出るひっかけ問題対策
営業保証金制度と保証協会(弁済業務保証金)制度は似ている点が多いため、宅建試験ではこの違いを問う「ひっかけ問題」が頻出です。
例えば
- 営業保証金は事務所開設「前」に供託、保証協会は事務所開設「後」に分担金納付
- 営業保証金は「供託所に直接」、保証協会は「保証協会へ分担金を納付」
このような細かい違いを抑えることで得点源にできます。
試験攻略アドバイス
この営業保証金制度は、次の点を重点的に押さえましょう。
- 金額の計算(本店1,000万円、支店500万円)
- 供託・届出の期限(免許取得3ヶ月以内、支店開設2週間以内)
- 取戻し時の公告(6ヶ月)
- 保管替えの流れ
- 還付の対象(宅建業取引債権のみ)
- 有価証券の評価額(国債100%、地方債90%、その他80%)
例題演習を最低5問、過去問形式で解いて、実際に数値と流れを手で書きながら覚えるのが効果的です。
また、保証協会との比較問題も出題頻度が高いので、違いを整理したまとめ表を自作しておくと得点アップにつながります。
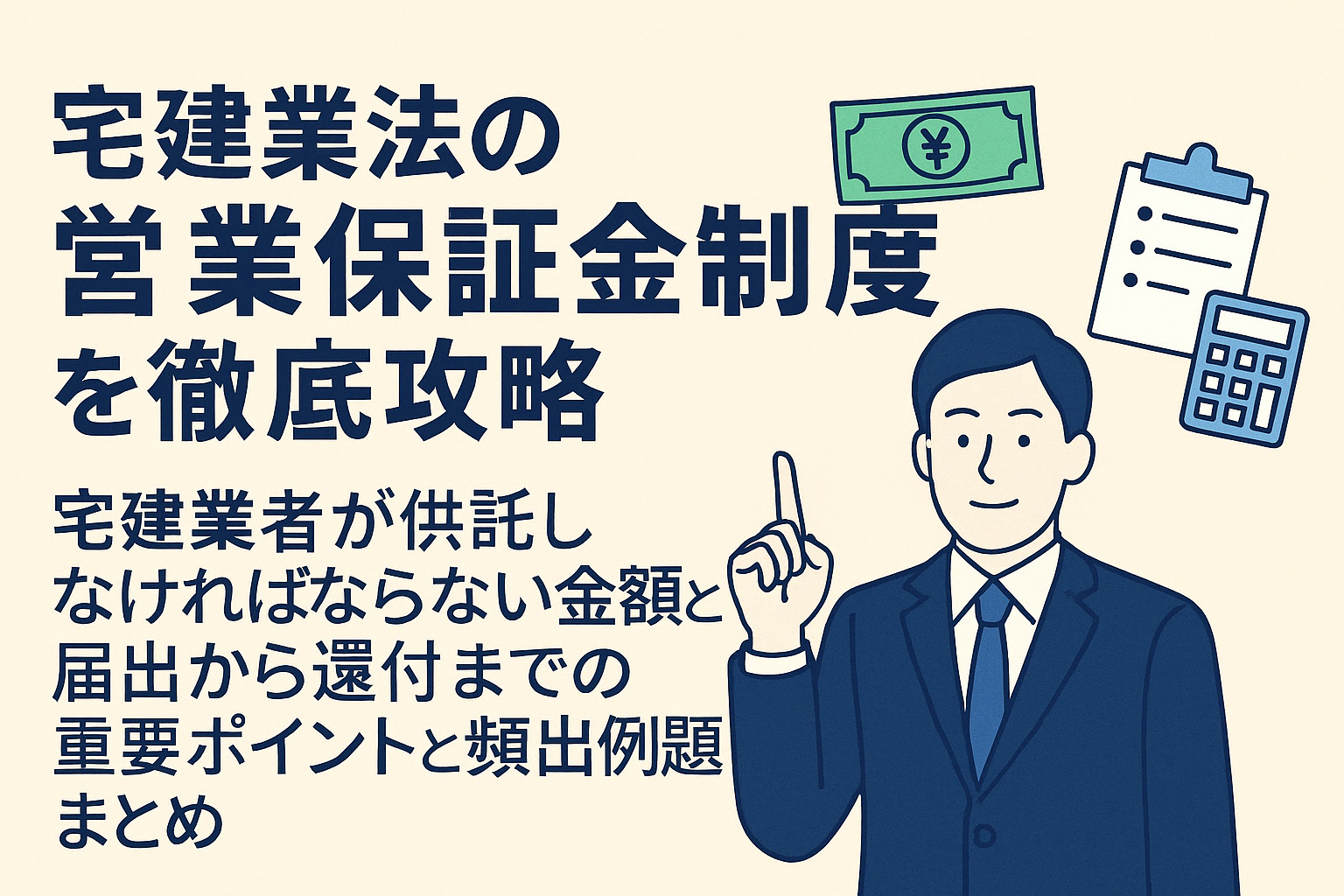
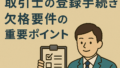
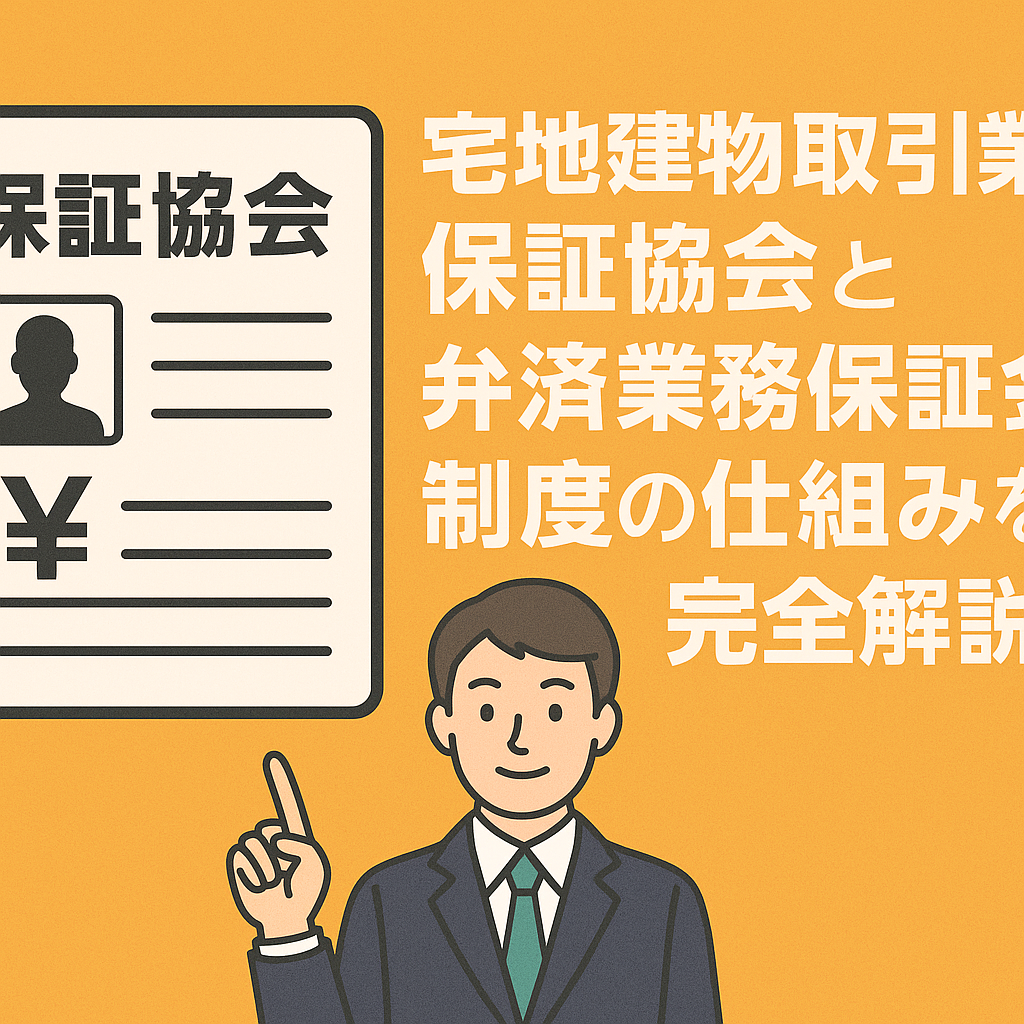
コメント