宅建試験受験者の皆さん、こんにちは。
本記事では宅建業法の中でも混同しやすい「営業保証金制度」と「弁済業務保証金制度」の違いについて、試験で問われやすい部分を徹底比較し、例題と解説を交えながら詳しく解説していきます。
どちらも不動産取引における消費者保護のための制度ですが、仕組みや金額、手続き、還付の流れなど、異なる点が非常に多いため、しっかり整理して覚えることが合格への近道です。
制度の目的と基本構造の違い
まずは両制度の基本的な位置づけと目的を整理しましょう。
営業保証金制度
宅建業者が自ら法務局の供託所に営業保証金を供託し、その財産的基礎を確保する制度です。
免許取得後、供託と届出をしなければ営業を開始できません。
弁済業務保証金制度(保証協会制度)
宅建業者が保証協会に加入し、分担金を納付。
協会がまとめて弁済業務保証金を供託し、消費者保護を図る団体保証制度。
分担金で済むため、個別供託より負担が軽いのが特徴。
供託額と納付金額の違い
営業保証金制度では、供託する金額が高額です。
営業保証金制度
- 本店:1,000万円
- 支店:1か所500万円
弁済業務保証金制度
- 本店:60万円(分担金)
- 支店:30万円(分担金)
この差額が大きく、資金負担の面からも保証協会制度の利用が一般的です。
供託の方法と納付先の違い
営業保証金制度
宅建業者が直接「本店所在地の最寄りの供託所」に供託。
現金または国債等の有価証券(国債100%評価、地方債90%、その他80%)で供託可能。
弁済業務保証金制度
宅建業者は直接供託せず、「保証協会に分担金を納付」。
保証協会が1週間以内に法務局の供託所に弁済業務保証金を供託する。
営業開始までの流れの違い
営業保証金制度
免許取得後、供託→免許権者への届出→営業開始
弁済業務保証金制度
免許取得後、保証協会へ加入→分担金納付→保証協会が供託→免許権者へ届出→営業開始
特に供託のタイミングの違いを整理しておきましょう。
還付の手続きと流れの違い
営業保証金制度
- 顧客が直接供託所に還付請求
- 供託所が還付実行
弁済業務保証金制度
- 顧客がまず保証協会へ認証申請
- 認証後、供託所へ還付請求
- 供託所が還付実行
この流れの違いは試験で頻出のひっかけポイント。
還付限度額の違い
営業保証金制度
宅建業者が実際に供託している金額が限度額。
弁済業務保証金制度
「営業保証金制度を選択していたと仮定した場合の供託金額」が限度額。
(本店1,000万円、支店500万円単位)
例題1
本店+2支店を持つ宅建業者が保証協会の社員である場合、弁済業務保証金の還付限度額は?
A. 120万円
B. 2,000万円
C. 60万円
D. 1,000万円
正解と解説
B。本店1,000万円+500万円×2支店=2,000万円。
還付後の補填方法の違い
営業保証金制度
還付で保証金が減った場合、宅建業者が不足分を2週間以内に供託し、さらに届出。
弁済業務保証金制度
保証協会がまず不足分を供託。
後日、宅建業者が保証協会に還付充当金を納付(通知から2週間以内)。
特別分担金の有無
営業保証金制度
特別徴収はない。
弁済業務保証金制度
還付が多発し、準備金でも補えないとき、保証協会は「特別分担金」を徴収できる。
通知を受けた日から1か月以内に納付しないと、社員資格を失う。
保証協会の必須・任意業務の違い
保証協会は、宅建業法で以下の業務を行うことが義務付けられています。
必須業務
- 弁済業務
- 苦情処理・結果の社員周知
- 宅建士研修
任意業務
- 手付金保管事業
- 一般保証業務
- 宅建業振興のための事業
例題2
保証協会の必須業務でないものはどれか。
A. 弁済業務
B. 宅建士研修
C. 苦情処理
D. 手付金保管事業
正解と解説
D。手付金保管事業は任意業務。
試験攻略ポイント
このテーマは次の点を整理しよう。
- 供託額と納付先
- 営業開始までの手続き順
- 還付の流れと限度額
- 不足補填・特別分担金
- 保証協会の必須・任意業務の区別
表にまとめるのもおすすめです。
総まとめ表
| 制度 | 営業保証金 | 弁済業務保証金 |
|---|---|---|
| 誰が供託 | 宅建業者 | 保証協会 |
| 金額 | 本店1,000万円 支店500万円 | 本店60万円 支店30万円 |
| 供託先 | 本店最寄の供託所 | 保証協会が供託所 |
| 営業開始 | 供託・届出後 | 分担金納付・届出後 |
| 還付請求 | 顧客→供託所 | 顧客→保証協会→供託所 |
| 還付限度額 | 実際の供託額 | 営業保証金相当額 |
| 不足補填 | 業者が直接供託 | 協会→宅建業者が還付充当金 |
| 特別分担金 | なし | あり |
| 廃業・取戻し公告 | 必要 | 必要(一部不要) |
最後に
宅建試験ではこのテーマが必ずと言っていいほど出題されます。
この制度比較を徹底的に理解し、例題を繰り返し解いておけば、確実に得点源になります。
おすすめ勉強法
- 制度別まとめ表を作る
- 過去問10年分をこのテーマだけ解く
- 引っかけ問題のパターンをストックする
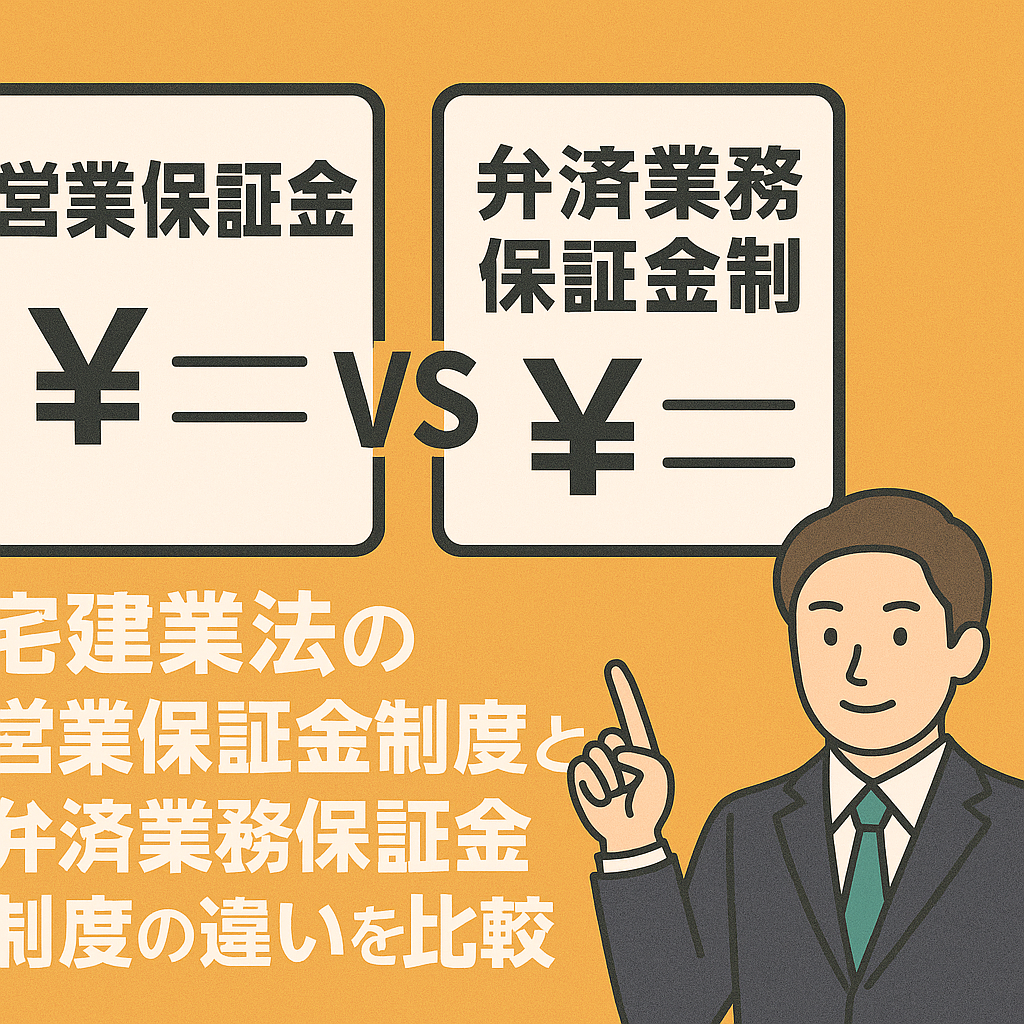
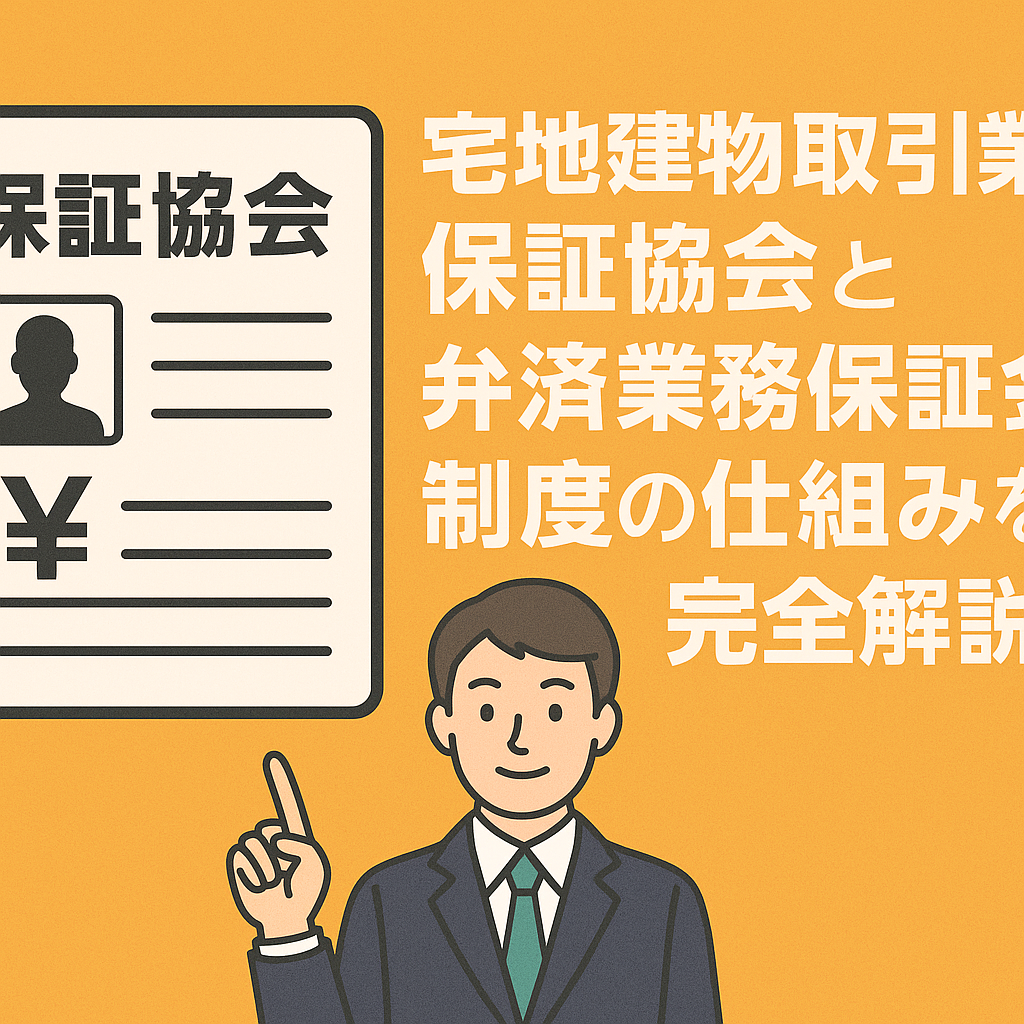
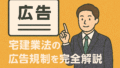
コメント