賃貸不動産経営管理士試験では、不動産経営に密接に関わる「保険」と「所得・課税」に関する知識が出題されます。火災や地震などのリスクに備える保険制度、そして不動産所得の計算や課税関係は、オーナーや管理士にとって実務でも重要なテーマです。この記事では、試験頻出ポイントを整理し、例題を交えながら解説します。
保険の意義と種類
保険は、万一の事故に備える相互扶助の制度であり、不動産経営のリスク分散に不可欠です。
- 生命保険(第一分野):人の生死に関する保険(終身・定期など)
- 損害保険(第二分野):火災保険、賠償責任保険、自動車保険など
- 傷害・医療保険(第三分野):ケガや病気を対象とする保険
賃貸住宅経営では特に損害保険が重要で、火災保険・地震保険・借家人賠償責任保険が中心となります。
✅ 学習ポイント
- 地震保険は火災保険に付帯して加入する仕組みで単独加入不可。
- 地震保険の保険金額は火災保険の30%~50%、建物は5,000万円、家財は1,000万円まで。
不動産所得と課税の仕組み
不動産賃貸から得られる収入は、原則として不動産所得とされ、所得税・住民税などの課税対象です。
不動産所得の計算式
不動産所得 = 収入金額 - 必要経費
収入金額には以下が含まれます。
- 賃料・地代・権利金・礼金・更新料
- 返還しない敷金・保証金
- 共益費(光熱費・清掃費など)
一方、必要経費として認められるのは固定資産税(賃貸用部分のみ)・修繕費・減価償却費・管理費・広告費・借入金利息などです。ただし、自宅に関わる費用や借入金の元本返済部分は経費になりません。
減価償却と修繕費
- 減価償却費:建物や附属設備の取得費を耐用年数に応じて費用化する仕組み。原則定額法で計算。
- 修繕費:通常の維持管理や原状回復費用は経費。資産価値を増す支出は資本的支出となり経費化できない。
青色申告のメリット
青色申告が承認されると、以下の特典が得られます。
- 最大65万円の青色申告特別控除
- 家族への給与を経費に算入可能(一定要件あり)
- 赤字の繰越控除(3年間)
消費税・所得税・住民税
- 消費税:住宅の賃貸は非課税だが、店舗や駐車場収入は課税対象。
- 所得税:不動産所得は総合課税され、翌年2/16~3/15に確定申告が必要。税率は5%~45%の累進課税。
- 住民税:一律10%。普通徴収と特別徴収あり。
法人化のメリット・デメリット
メリット
- 税率軽減(法人税率は30%前後、個人は最高55%)
- 所得分散による節税
- 融資面での信用度向上
デメリット
- 設立費用・税理士報酬が必要
- 赤字でも均等割課税(最低7万円)
- 社会保険加入義務
【例題1】地震保険
Q:地震保険は火災保険と独立して契約できるか。
解答:できない。
→ 地震保険は火災保険に付帯して加入する仕組み。
【例題2】必要経費
Q:次のうち、不動産所得の必要経費として認められないものはどれでしょうか。
- 賃貸用マンションの固定資産税
- 自宅部分の固定資産税
- 賃貸経営に関わる税理士報酬
- 借入金の利息(賃貸用建物分)
解答:2. 自宅部分の固定資産税。
【例題3】修繕費か資本的支出か
Q:築20年のアパートで外壁を全面的に改装し、耐用年数が10年延びる場合、この費用は修繕費か資本的支出か。
解答:資本的支出。
→ 建物の耐用年数を延長する支出は資本的支出となる。
【例題4】消費税
Q:次の収入のうち消費税が課されるのはどれでしょうか。
- 住宅の賃料
- 駐車場収入
- 住宅の敷金(返還されるもの)
- 土地の譲渡代金
解答:2. 駐車場収入。
まとめ
- 保険分野では火災保険・地震保険・借家人賠償責任保険を整理。
- 不動産所得の計算は「収入-必要経費」。何が経費かを判別する問題が出やすい。
- 減価償却・修繕費・青色申告の特典は試験でも実務でも重要。
- 消費税の非課税・課税の区別は頻出。
👉 数字や仕組みを暗記するだけでなく、「なぜ経費になるか」「どの税がかかるか」を具体的に理解することが、合格への近道です。
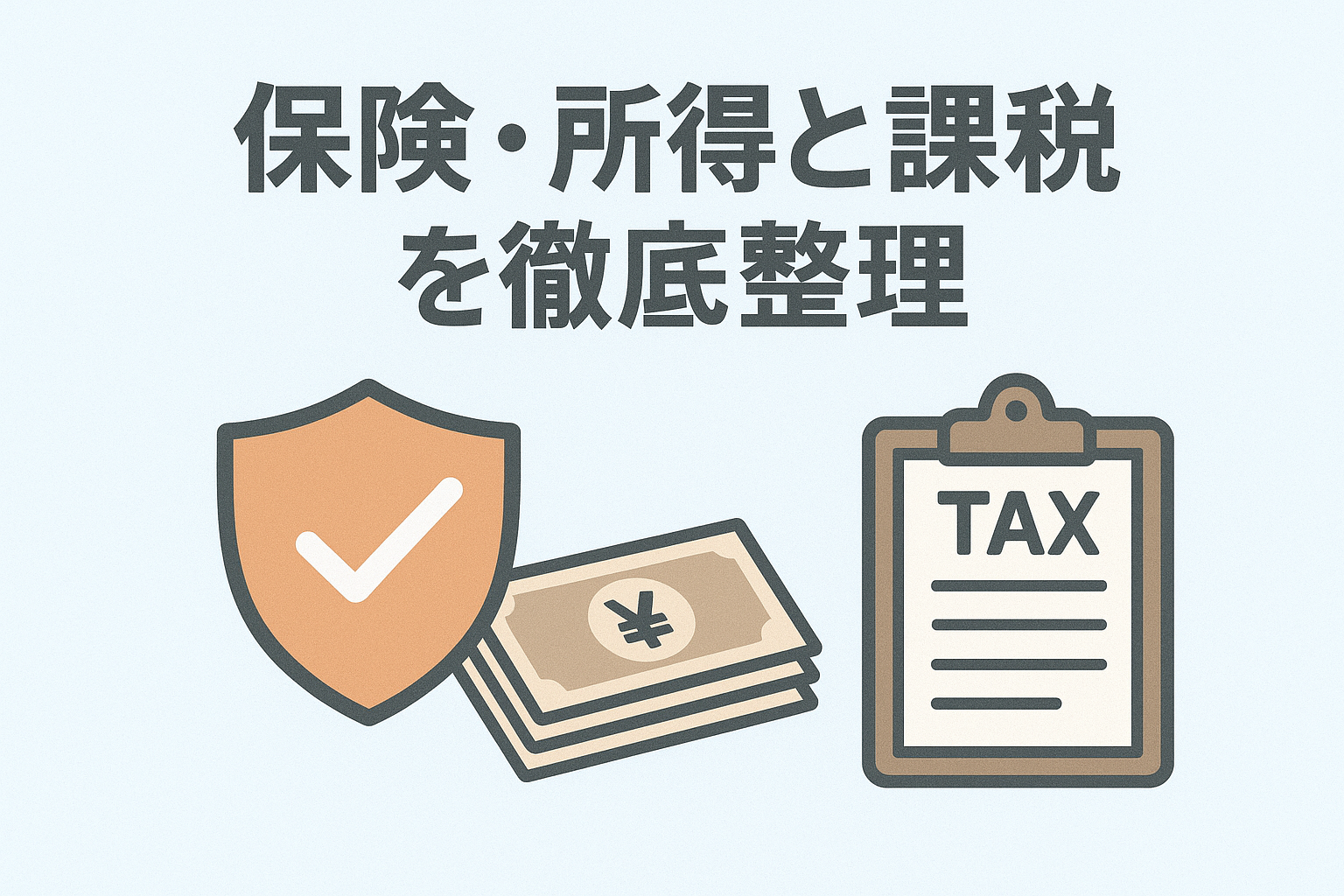
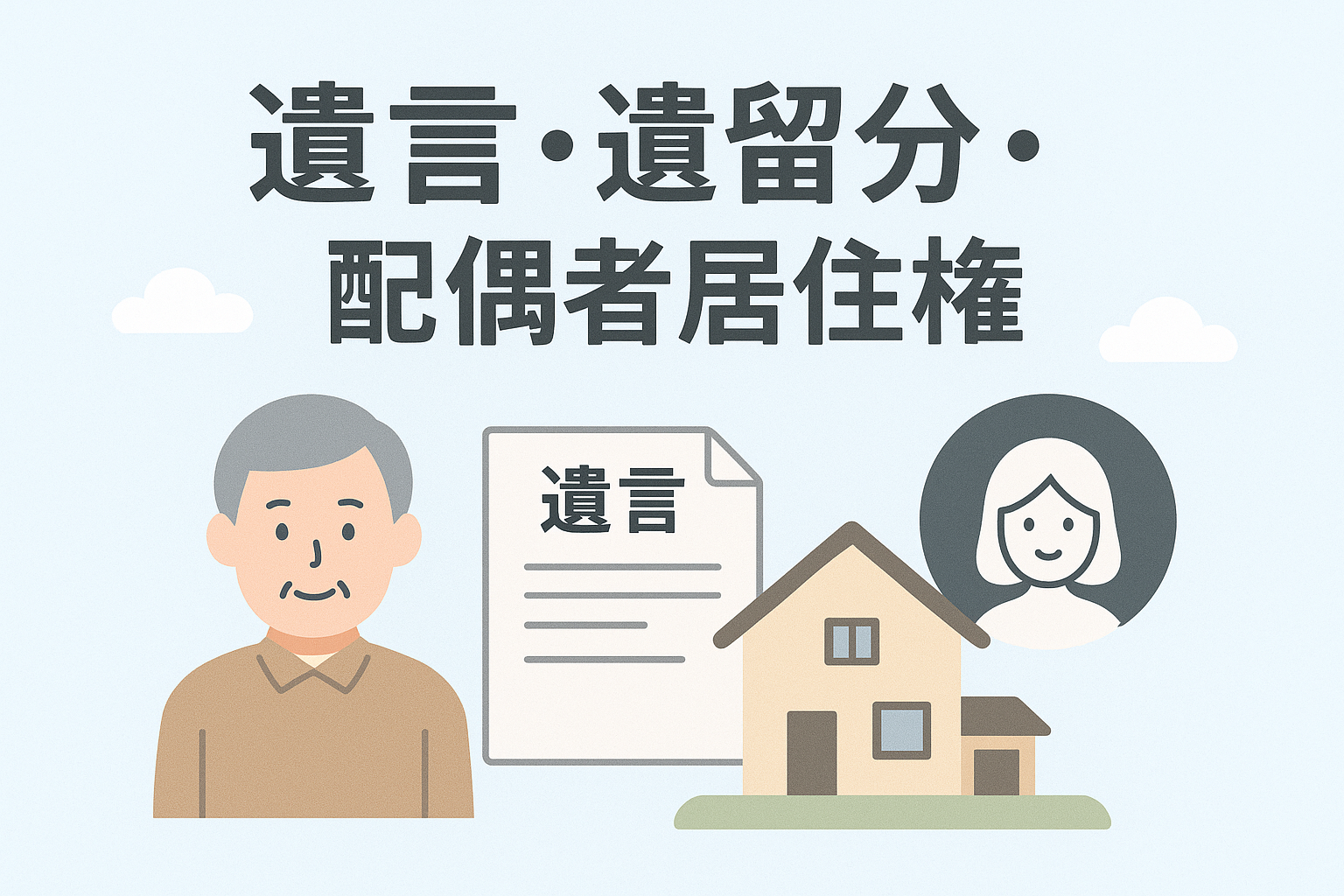

コメント