賃貸不動産経営管理士試験では、民法や不動産登記法に関する「権利関係」の出題も多く、その中でも**抵当権(ていとうけん)**は重要テーマの一つです。
抵当権は、住宅ローンや不動産担保取引など、賃貸経営の現場にも密接に関係する制度です。
今回は、抵当権の基本から実務上の注意点、試験で問われやすい論点までを整理して解説します。
抵当権とは?(民法369条)
抵当権とは、「債権を担保するために、債務者や第三者の不動産に設定し、その占有を移さずに、その不動産から優先的に弁済を受ける権利」です。
■ ポイント
- 債務者が返済できない場合に、抵当権者(=お金を貸した人)は競売によって優先的に弁済を受けられる。
- 不動産を引き渡す必要はなく、所有者はそのまま使用・賃貸することができます。
- 抵当権は、登記によって効力を生じる(民法177条)。
抵当権設定の具体例
例えば、オーナーAが所有するアパートを担保にして銀行から融資を受ける場合、Aはそのアパートに抵当権を設定します。
もしAが返済不能になった場合、銀行は裁判所を通じてそのアパートを競売にかけ、売却代金から優先的に回収します。
抵当権の特徴
① 不動産に対する担保権
抵当権は土地や建物などの不動産にのみ設定できます。
動産や債権には通常、質権など別の担保権が利用されます。
② 占有を移さない
抵当権は、設定後も債務者が不動産を使用・収益できます。
これが、質権(目的物を引き渡す)との大きな違いです。
③ 物上代位
抵当不動産が保険金や売却代金などに変わった場合でも、抵当権者はその代金に優先弁済権を行使できる(民法372条)。
→ これを「物上代位」といいます。
抵当権の効力の及ぶ範囲
抵当権の効力は、原則として目的物の一体性を保つものにも及ぶとされています。
■ 具体的には
- 建物に抵当権を設定した場合 → 附属設備(エレベーター・給湯設備など)にも効力が及ぶ。
- 土地に抵当権を設定した場合 → その上の建物には原則として及ばない(別登記が必要)。
抵当権と賃貸借の関係
賃貸不動産経営管理士試験では、この「抵当権と賃貸借の関係」が特に狙われます。
■ 登記の前後関係がカギ!
- 賃貸借契約が先、抵当権が後の場合
→ 借家人(入居者)は、抵当権実行後も引き続き居住できます。 - 抵当権が先、賃貸借契約が後の場合
→ 抵当権実行により買受人に所有権が移転すると、借家人は退去を求められる可能性があります。
(ただし、借地借家法の適用がある場合には保護されるケースもあり)
抵当権の消滅
抵当権は、次の場合に消滅します。
- 被担保債権(ローンなど)が返済されたとき
- 抵当不動産が競売により売却されたとき
- 抵当権者が放棄したとき
- 混同(債権者と債務者が同一人になる)したとき
抵当権に関する試験出題ポイント
| 分野 | 内容 | 出題傾向 |
|---|---|---|
| 抵当権の定義 | 占有移転を伴わない担保権 | 基本問題 |
| 登記 | 登記しなければ第三者に対抗できない | 高頻度 |
| 物上代位 | 保険金・売却代金にも効力が及ぶ | 応用問題 |
| 賃貸借との関係 | 登記の前後関係で入居者保護が変わる | よく出る |
| 抵当権消滅 | 弁済・競売・放棄・混同 | 確認問題 |
例題
例題:
Aは自己所有の賃貸マンションに銀行の抵当権を設定し、その後、入居者Bと賃貸借契約を結んだ。
Aがローンを返済できず競売になり、Cが落札して所有権を取得した。
この場合、Bはマンションに住み続けることができるか?
解答:
できません。
抵当権設定登記が先で、賃貸借契約が後の場合、買受人CはBの賃貸借契約を引き継がず、退去を求めることができます。
まとめ
抵当権は、民法の中でも「不動産の担保」に関する基本的な制度です。
試験では、
- 登記による効力の発生
- 物上代位
- 賃貸借との関係(登記の前後関係)
の3つが特に重要ポイントです。
賃貸経営においても、所有物件に抵当権が設定されている場合、万一の競売で入居者が影響を受けることがあります。
実務と試験の両面から、抵当権の仕組みをしっかり理解しておきましょう。
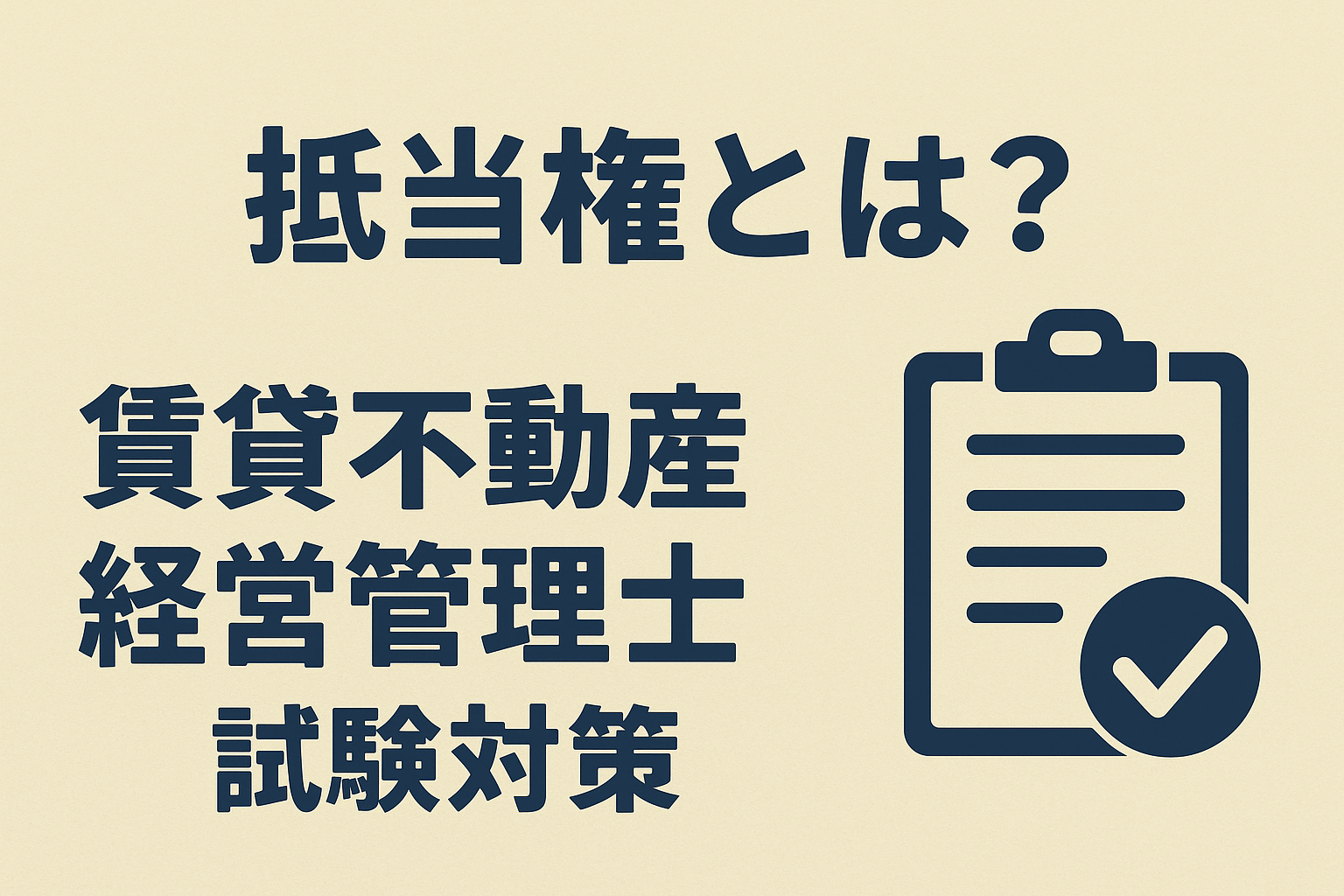
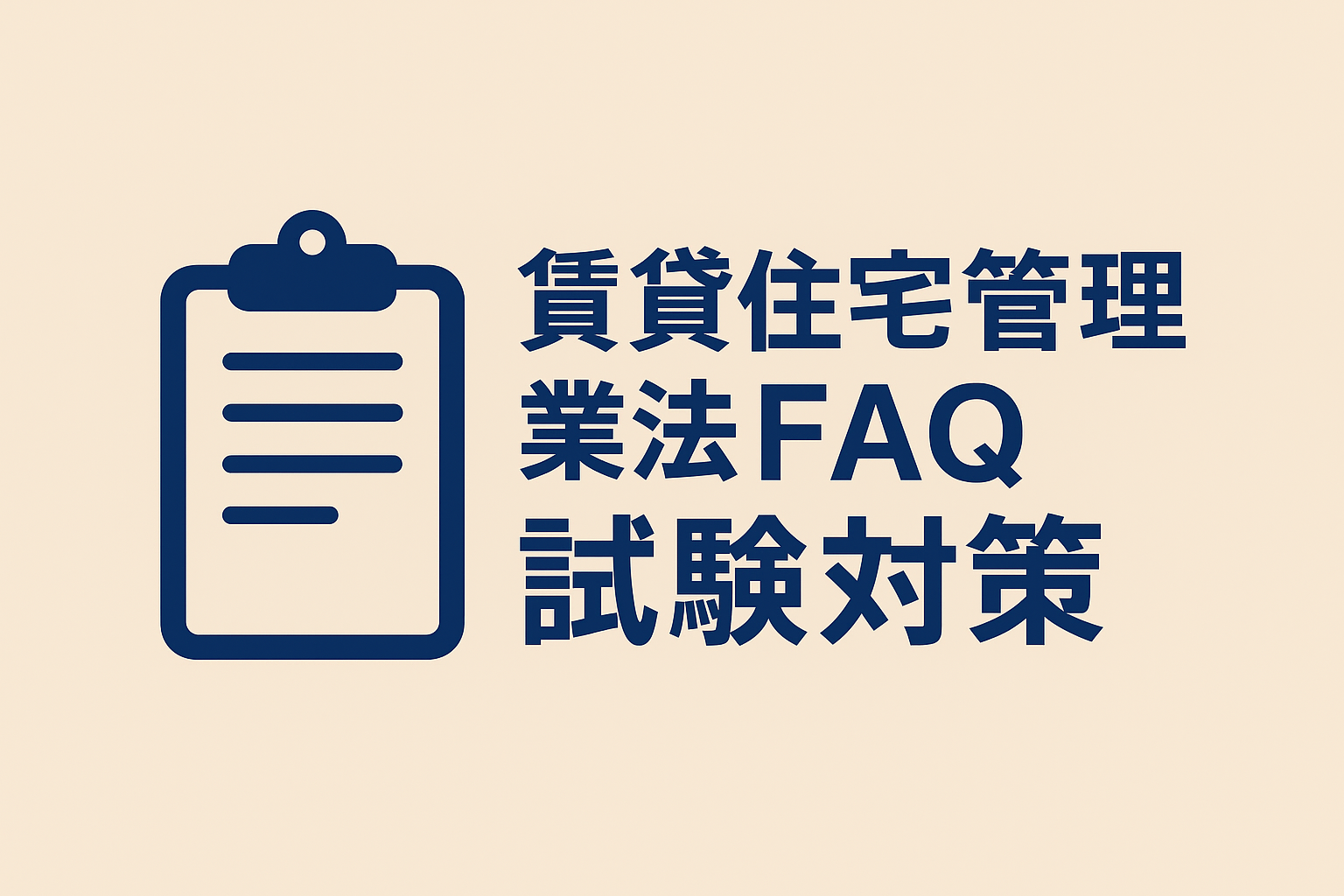

コメント