はじめに
賃貸住宅管理業法の中でも、「特定賃貸借契約(マスターリース契約)」は近年の試験で頻出のテーマです。
サブリース業者による誇大広告や不当な勧誘など、社会問題化したトラブルを背景に、法による規制が強化されています。
本記事では、特定賃貸借契約の定義・除外対象・勧誘者の範囲・誇大広告や不当勧誘の禁止について、具体例とともに徹底解説します。
最後に試験対策用の例題も掲載していますので、理解度チェックにお役立てください。
特定賃貸借契約とは?(マスターリース契約の定義)
「特定賃貸借契約」とは、賃貸住宅を第三者に転貸することを目的として締結される賃貸借契約をいいます(賃貸住宅管理業法2条4項)。
この契約に基づき転貸事業を行う者を「特定転貸事業者(サブリース業者)」と呼びます。
💡ポイント
- 賃借人が転貸事業を「反復継続的に」行う場合、事業性があると判断されます。
- 個人が一時的に友人などに貸すケースは「特定賃貸借契約」に該当しません。
- 営利の意思の有無は、契約内容や取引の状況から客観的に判断されます。
特定賃貸借契約から除外されるケース
国土交通省令により、次のような「密接な関係にある者」は特定賃貸借契約の対象外です。
| 賃貸人の属性 | 除外される関係者 |
|---|---|
| 個人 | 賃貸人の親族、または親族が役員の法人 |
| 会社 | 親会社、子会社、関連会社 |
| 登録投資法人 | 資産運用会社の関係会社 |
| 特定目的会社(SPC) | 管理委託先の関係会社 |
| 不動産特定共同事業組合 | 業務執行者およびその関係会社 |
| 特例事業者 | 関連する不動産特定共同事業者や小規模不動産事業者 |
再転貸も「特定賃貸借契約」に該当
サブリース業者(A社)がオーナーと特定賃貸借契約を結び、その住宅を別の事業者(B社)に貸し、さらにB社が第三者に転貸するような再転貸スキームでも、
A社とB社間の契約は特定賃貸借契約に該当します。
つまり、事業としての転貸であれば、階層が深くなっても規制の対象になるということです。
パススルー型スキームの扱い
「パススルー型」とは、賃料がそのままオーナーに渡り、サブリース業者が手数料を取らない形態です。
しかし、実際に運用益や管理報酬などで利益を得る構造があれば、営利目的があると判断され、特定賃貸借契約に該当します。
借上社宅の場合の取り扱い
企業が社宅として賃貸住宅を借り上げ、従業員に提供するケースでは、企業は転貸事業者に該当しません。
これは、営利目的ではなく福利厚生目的だからです。
一方で、社宅代行業者がオーナーと契約して企業に貸す場合は、代行業者が営利目的を有しているため「特定転貸事業者」となります。
勧誘者とは?
特定転貸事業者から委託や依頼を受けてマスターリース契約の勧誘を行う者を「勧誘者」といいます。
これは建設業者・不動産業者・金融機関・コンサルタントなど、幅広い事業者が該当します。
💡具体例
- サブリース業者から依頼を受けて勧誘を行う建設会社
- 親会社・子会社関係のサブリース業者を紹介する不動産会社
- サブリース業者の資料を使って事業説明を行う金融機関
- 紹介料を受け取って顧客を誘導するオーナー
一方、単なる「紹介」(契約内容に触れない紹介行為)は「勧誘」には当たりません。
誇大広告の禁止(第28条)
■禁止の趣旨
オーナーが誤解して契約を締結することを防ぐため、サブリース業者および勧誘者には、誇大広告や虚偽広告が禁止されています。
■禁止される主な広告内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 家賃条件 | 実際より高い保証額・誤解を与える利回り表示 |
| 維持保全 | 実際に行わない修繕内容の記載 |
| 費用負担 | オーナー負担を隠す「費用ゼロ」表示 |
| 契約解除 | 解約できないのに「30年保証」と表示するなど |
💡打消し表示のルール
- 強調表示のすぐ近くに配置し、同等の大きさ・色で表示
- Web広告でも同一画面内に明記
- 「利回り○%」などの断定的表現には、リスク説明を併記
■違反例
- 「30年家賃保証」「家賃下落なし!」
- 「修繕費ゼロ」「維持費一切不要!」
- 「絶対に損しない不動産投資」
これらは、実際の契約内容と異なるため著しく事実に相違する表示とされ、法28条違反となります。
不当な勧誘の禁止(第29条)
サブリース業者や勧誘者は、契約の締結や解除に関して次のような行為をしてはなりません。
(1) 事実を故意に告げない・不実を告げる行為
オーナーの判断に影響を与える重要事項をあえて隠す・嘘をつく行為です。
■具体例
- 家賃減額リスクを説明せず「家賃は下がりません」と言う
- 原状回復費用のオーナー負担を隠す
- 契約解除ができるかのように説明する
- 「必ず利益が出る」「絶対に損しない」など断定的な説明を行う
これらは**罰則の対象(42条2号)**です。
(2) 相手方の保護に欠ける行為(規則43条)
こちらは罰則はありませんが、法的に禁止されています。
| 禁止行為 | 内容 |
|---|---|
| 威迫 | 「帰さない」「契約しろ」と強要する行為 |
| 迷惑時間勧誘 | 午後9時〜午前8時の電話・訪問勧誘 |
| 長時間勧誘 | 深夜や勤務中の執拗な説明 |
| 再勧誘 | 契約を断った後の再訪問・再電話 |
これらの行為は「相手方の自由意思を妨げる」ものであり、倫理違反として行政指導の対象となります。
建設業者・不動産業者が関わる場合の留意点
建設請負契約や不動産の売買契約とセットでマスターリース契約を勧誘するケースでは、特にリスク説明が重要です。
建設契約後にサブリース契約のリスクを知らされた場合、オーナーは多額の債務を抱えた状態で後戻りできなくなります。
したがって、勧誘段階でリスク情報を開示する義務があります。
国交省のガイドラインでは、
「サブリース契約リスク説明書」を交付し、内容を理解させることが望ましいとされています。
💡例題で理解を確認!
例題1
サブリース業者が「30年間家賃保証」と広告したが、契約内容には5年ごとに見直し条項があった。この広告は適法か?
→ 不適法(誇大広告)。家賃見直しの旨を明示しなければ法28条違反です。
例題2
建設会社が自社で建てるアパートのマスターリース契約を勧誘する際、家賃減額リスクを説明しなかった。
→ 不当な勧誘(事実不告知) に該当します(29条1号)。
例題3
オーナーが「契約しません」と伝えたにもかかわらず、業者が翌日再度訪問した。
→ 再勧誘行為 に該当し、法29条2号違反です。
例題4
社宅代行業者が企業に物件を貸し出して従業員に住まわせる。この社宅代行業者は特定転貸事業者に該当するか?
→ 該当する。 代行業者は手数料を得るため営利目的があるため(解釈2条5項)。
まとめ:サブリース規制の本質を理解しよう!
✅ 特定賃貸借契約=転貸事業を目的とした賃貸借契約
✅ サブリース業者・勧誘者には広告・勧誘規制がある
✅ 誇大広告(虚偽・誤認)は厳しく禁止(第28条)
✅ 不当勧誘(事実不告知・威迫・再勧誘)も禁止(第29条)
✅ 罰則の対象となるのは「事実不告知・不実告知」
おわりに
サブリース契約は「家賃保証で安心」と思われがちですが、実際にはリスクの説明不足によるトラブルが多発しています。
賃貸不動産経営管理士としては、オーナーが適切に判断できるよう、特定賃貸借契約の法的枠組みと広告・勧誘規制を正確に理解することが求められます。
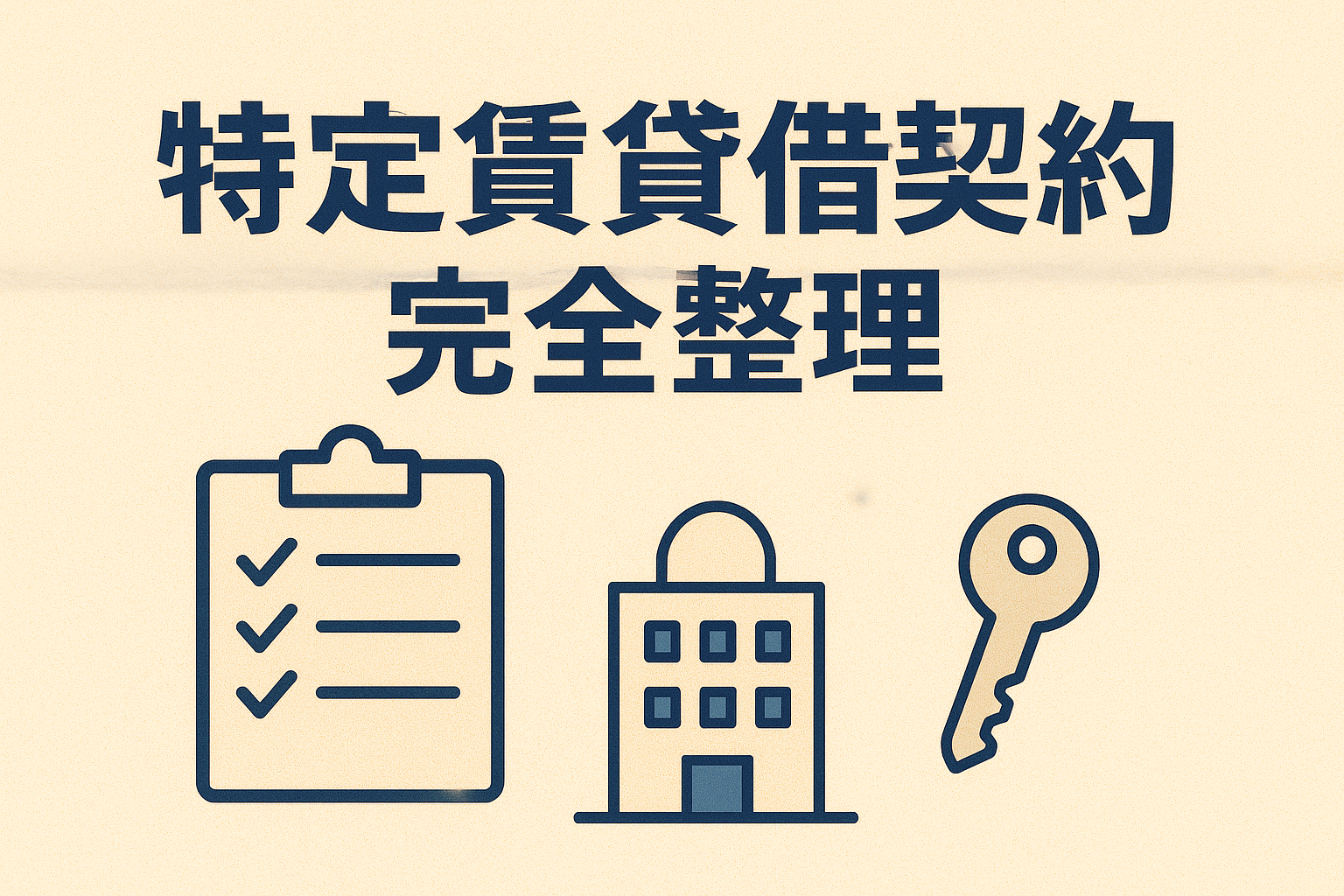


コメント